HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事ライン】
note 中西氏
いかに「自分自身を事業成長の手段にする」か
公開日:2024.07.29
- 記事をシェアする
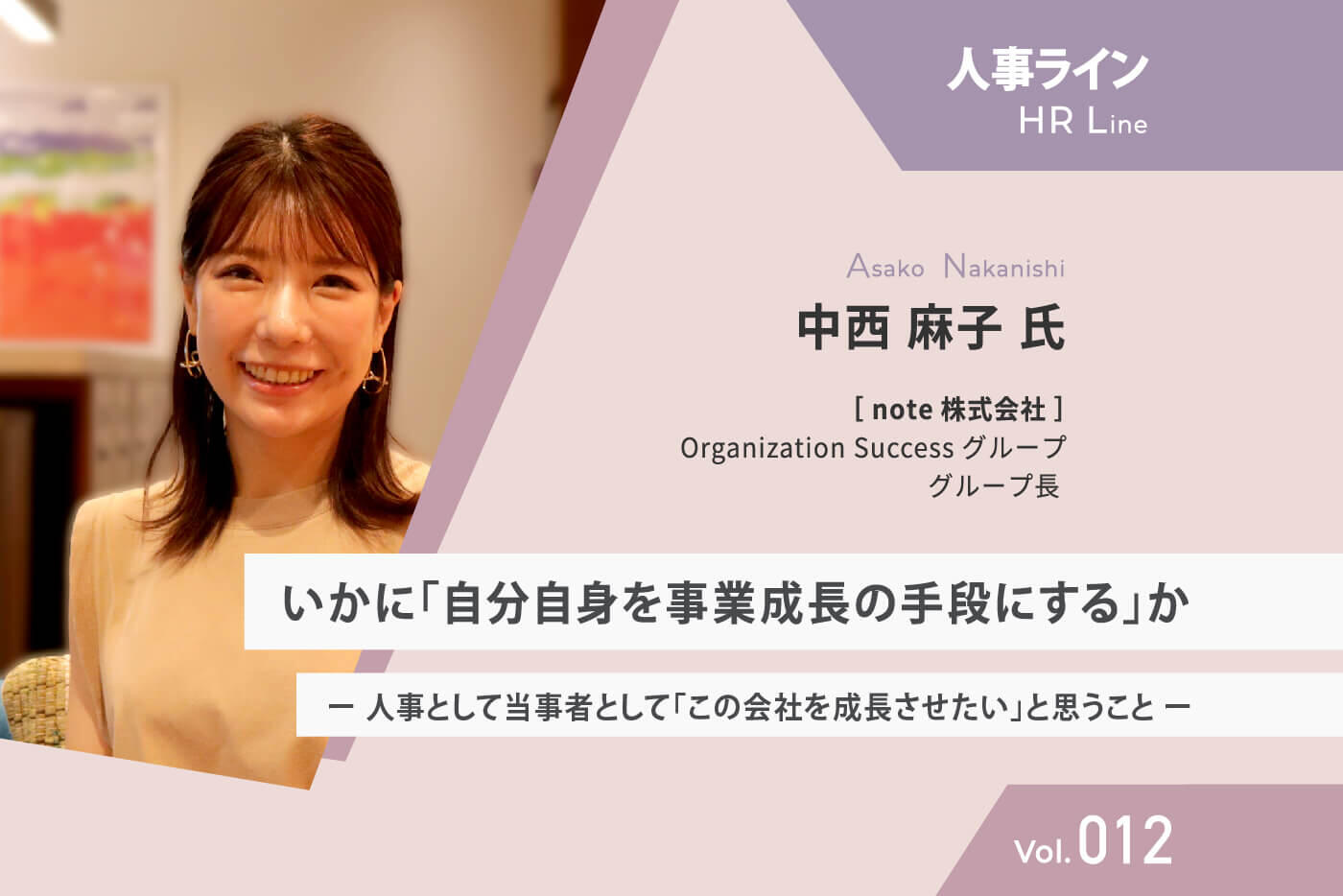
note株式会社
Organization Successグループ
グループ長
中西 麻子 氏
「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」さまざまな企業の人事パーソンインタビュー『人事ライン』。今回は、note株式会社で人事領域のグループ長を担当されている中西 麻子さんです。
これまで環境が異なる3社の人事でのご経験やそこで得たものや気付き、noteでのカルチャー浸透やHRBP(HRビジネスパートナー)の立ち上げのこと、また人事への想いなどをお話いただきました。
― これまでのキャリアと現在の役割を教えてください。
2012年に大学を卒業し、ヤフーに入社しました。大学時代から人事をやりたくて、就職活動の面接でも「人事をやりたいです」と話をしていたんです。最初の配属は経営企画でしたが、1年目の間に人事に異動しました。労務からスタートしHRBPや人事企画などの人事労務領域を7年間経験しました。その後、従業員が150人くらいの会社にリファラル採用(自社の社員から友人や知人などを紹介してもらう手法)で人事として転職し、初めてマネジメントの経験もしました。そこで人事組織のマネージャーを2年弱経験した後、現在のnoteにジョインし、現在4年程経ったところです。noteでは「Organization Successグループ」という、人事・労務領域を束ねている組織のグループ長を担当しており、採用、組織開発、労務、またHRBP体制や人材育成についても担っています。
― 人事のキャリアを積まれていらっしゃいますが、現在のnoteに転職をしたきっかけを教えてください。
最初の転職をしたときは、会社の従業員規模が7,000人から150人に変わり、同じ人事でも立ち回り方や付加価値の出し方などが全く違いました。決まった領域だけでなく、幅広くさまざまなことに対応をしていくことについてはポジティブに捉えていて、縦割りではなく全体を見ることができる人事の形はとても有意義な経験でした。そのような中で「自分自身がより当事者としてミッション・ビジョン・バリューに共感し、会社の成長に関わっていけるところにチャレンジしたい」という想いが強くなっていきました。そんな時に出会ったのがnoteでした。
創業者である社長との面接で「noteをこういうふうに大きくしていきたい」というビジョンの話を直接聞いた時、その言葉にとても共感し「人事という立場からだけではなく、一当事者としてこの会社を成長させていきたい!」と純粋に思えたんです。noteはミッションドリブン(ミッションに基づいて意思決定をすること)で「こういう価値を社会に生み出していこう、そのためにこういうことをやっていこう」という考え方が強い。そういうところが自分に合っていると思いました。
入社する前は「noteってブログサービスの会社なのかな」くらいにしか思っていなかったのですが、社長の話を聞いてみると、そんなことは全くなかったんです。創作というと少し言葉が堅苦しいかもしれないのですが、ちょっとした気付きや想いの発信、それこそ料理をしながらする鼻歌も創作だと言います。そういった「あらゆる創作をプラットフォームとして生み出し届けるために、世の中の仕組みを変えていきたい」という大きなミッションを持つ会社でした。それを成し遂げようとすると、従業員数も今の規模では達成できないだろうし、戦う相手も強豪になってくる。組織としてもどんどん成長させて、確固たる強い組織をつくっていかなければならない。そういうチャレンジングな部分が会社として組織としても大きいのだろうなということがイメージでき、やりがい、成長の幅、そして人事として貢献のしがいがあると思えたところが大きかったです。

私は、人事は総合格闘技だと思っているんです。例えば採用だけ、組織開発だけ、人材育成だけではなくて、あらゆる領域の総合格闘技として会社の成長にコミットできるのが楽しいですし、やりがいがあります。
大きな規模の会社で人事だけで100人、採用部で40人というような組織についても、自分たちがやったことのインパクトの大きさを実感するシーンがあったり、たくさん学ぶこともあると思います。一方で人事としてのおもしろさという観点でいうと、個人的には今のような小さな組織の中であらゆる手段を駆使できるというのが、やっぱり一番やりがいがあるなと思っています。
― 3社にわたり人事のキャリアを積まれていらっしゃいますが、それぞれで印象に残っていることを教えてください。
これまで3社、規模もフェーズも違う会社を経験しましたが、振り返って思うと、それぞれに印象に残っている仕事があります。
ヤフーでは私が新卒3年目の時に、新たな雇用制度を取り入れるプロジェクトのリードを担当したことです。7,000人もいる会社で雇用制度を変えるということは影響度がとても大きく、論点などについて考慮しなければならないポイントもたくさんあり、人事としてすごく鍛えられました。
2社目では、入社直後から右も左も分からない中で、さまざまな挑戦をさせてもらいました。例えば、入社したその月に全社のマネージャー合宿の企画運営のリードをやることになり、事業と組織の成長にどういう形でマネージャーを巻き込むとよい方向につながるのかをWhy、Whatから考えアウトプットしました。自分のコンフォートゾーンを出るような、わからないけれどもとりあえずやってみるというような経験が許される環境だったので、すごく学ぶことが多かったです。
現在のnoteで、直近のこととしては2023年の12月、上場後初めての新年度を迎えるタイミングで全社の組織体制を大きく変えたんです。これまで組織責任者、組織の長は取締役や執行役員が兼務していたのですが、 会社としても組織としても成長していくために、これからは権限移譲も必要だということを踏まえて、新たに組織長を7名抜擢しました。全社の体制をつくり、経営会議や組織体制などを一気に変えて、経営陣はいわゆる経営の業務に集中し、執行の部分は新たに抜擢された組織長でやっていく。もちろん経営陣と一緒に考えていったものではありますが、とても大きな仕事でした。
― 組織体制が変わる中で、人事として方針を伝えたり、仕組みや制度を変えることもたくさんあると思います。現場への理解や浸透において、工夫していることはありますか。
人事だけがその浸透に取り組むものではないと思っていて、経営や各部門長はもちろん、各部門内でキーマンを見つけて一緒に取り組む、また、そもそも組織のコアになるようなキーマンとなりうる人材を採用するなど、「人事だけが取り組むことではない」という巻き込み方を意識しています。また、半年前にHRBPの体制をつくり、各組織に人事メンバーがHRBPとしてつき、普段から部門のパートナーとして相対しています。こうした中で、普段からコミュニケーション接点、接触面積を持ちながら、方針や施策についても徐々に浸透させていくというような体制の工夫をトライアンドエラーしています。メンバーからも「この半年、成長を実感した」と言ってもらえ、HRBP体制を開始したことは人事としても引き出しが増えたと思っています。
― 浸透というと、中西さんが大事にされているカルチャーについても課題になっているとよく聞きます。現状、従業員の方は基本的に中途採用のみと伺いましたが、さまざまなバックグラウンドがある方がジョインされている中でのカルチャーの浸透は、どのようにされているのでしょうか。
カルチャー浸透については、従業員ジャーニーマップを描き、入社前の段階からミッションについての接触面積をきちんと設けていこうという方針にしています。入社前から採用候補者に情報が届くようにすることがとても重要だと思っており、ミッション・ビジョン・バリューに沿った記事の発信などをしているので、noteの目指すもの、ミッションやそこに紐づくバリューなどを理解した上で面接に来て選考を受けていただくことが多いです。入社後もワークショップを行い、日々の業務でのバリューの活かし方やそれがどう自分の成果につながるのかを考える場をつくっています。また、全社員が集まるミーティングを毎週行っていて、バリュー事例の共有をしたり、経営メンバーからミッションに関する発信もあります。
意識していることは、そのようなことを点ではなく線でつないで設計するということです。ワークショップやミーティングでの発信だけではなく、評価制度にはパフォーマンスとバリュー両方の構築をイーブンで設けるなどつながりを意識しています。
― 現在の人事の課題を教えてください。
今、時間的に目の前のことで手一杯で、先を見据えたアクションがあまりできていないということが、組織としてもそうだし、組織長としても課題だと思っています。毎日さまざまなことが起こるので、変化が多く楽しいのですが、将来に向けてプラスを生み出していくとか、その仕掛けをつくっていくことにももっとチャレンジしたいと考えています。私がnoteに入るときに共感したビジョンを見据えて、そこに向けて今から取り組んでおけることがあると思っているものの、組織として実行しきれていないというところが、もどかしい部分だと思っています。単純なリソースの問題だけではないのかもしれないのですが、いかに時間軸を長く持つかというところは、メンバーと共に意識していきたい課題です。
私がnoteに入社した時はコロナ禍だったのですが、そのときに、ご挨拶1on1という形で経営陣、メンバー全員と話をさせてもらって、経営からみる課題と現場から見る課題を整理して取り組むアクションを考えるところからスタートしました。
今は上場後のフェーズとして組織が変わっていくタイミングでもあるので、本来であれば、当時のような全員と話をするような取り組みをやりたいのですが、全く時間がとれていない。一方で今は、私自身がやらなくても、HRBPである人事メンバーが現場メンバーと1on1をしたり、部門長と定期的に話してもらうことで解決できる部分もあるかなと、仕組みを模索中です。
― 人事で楽しい、やりがいを感じるとか、自分の価値を出せたと思う瞬間はどのようなときでしょうか。

例えば「採用をして、その人が入ったことで組織も活性化され成果も出た」「新たな制度を導入して会社のカルチャーが変わってきている」というようなことは分かりやすい成果だとは思います。そういったことももちろんありますが、ちょっとした日々の変化を生み出すのが人事の仕事かなと思っているんですよね。例えばHRBPとしては、人事としての知見や情報をインプットして部門長が適切で質の高い判断ができるようサポートするといった、組織をよくするちょっとしたことも変化の一つではないかと。
そういう日々の変化を楽しみながらやっていこうという話をメンバーにもしていて、大きなことをやり遂げたとかではなくても、日々のちょっとした自分が生み出す変化でやりがいを感じる瞬間はあるんだろうなとは思っています。
人事って派手な仕事だけではないので、日々どういう部分に楽しさを持っていくかということや、自分自身のキャリアの価値をどういうところに感じているのか、他の会社の人事の方の考え方も知りたいですね。
― 日々のちょっとした変化も含めて、人事の成果は目に見えづらいものが多いと思います。それを感じるような環境や機会をつくっていますか。
日々の1on1もそうですが、全員でオフィスに集まって、お互いのバリューを発揮したことをたたえたり、「あれは大変だったよね。次にこういう学びがあったよね」というような振り返りをする機会を設けるようにしています。また、リモート勤務がベースなこともあり、毎朝Zoomで朝会を30分くらいやっていて、クイックなコミュニケーションを取れるようにしています。効率も重視しつつ、接点を多く設けておくことを意識しています。
「採用のことは採用担当メンバーで」というように分けることもできますが「何のためにこの採用をしているのか」「組織がこういう状況だからこういう人を採用しないといけない」というようなことは、採用チームよりもHRBPのほうが分かっているんですね。メンバーには、全体のつながりや全体像を把握するからこそ分かるそれぞれの業務の価値を理解してほしいので、そこは全員で行っています。
― 中西さんのこれからのキャリアプランやチャレンジしてみたいことを教えてください。
私は「何がなんでも出世したい!」とかそういうタイプではなく、いかに「自分自身を手段にする」か、それに徹するかという考えでやるべきことをやってきたタイプです。現状は正直、キャリアにおいても自分の中で明確にあるわけではなく、模索中です。
ただ一つ言えることは、私は会社を成長させたいという想いがすごく強いということで、自分は会社を成長させるための手段となれるように頑張りたいです。そのために人事の知識はもちろん、経営や経営企画などについても勉強し視野を広げていきたいです。それだけ自分自身の引き出しが増えるので自分の価値も上げられるのではないかと思っています。
― 中西さんのおっしゃる「手段」はポジティブな手段ですね。ご自身としても組織としても「手段」となり、それを広げていくような感じがします。その「手段に徹する」と言い切るようになったのは、いつ頃からなのでしょうか。
ヤフーでHRBPを担当していたときからでしょうか。まだHRBP組織の立ち上げ期の中で、まだ新卒2年目の私がある組織を担当したときです。当時の私は何も分からない中で、ただの伝書鳩で精一杯になっていて、当時の役員に叱咤を受けた経験があります。今振り返るとその当時私がすべき行動としては人事で決まった方針をそのまま伝えることではなく、現場にはどういった課題があって、それを解決できる手段はないのかなど、WhyからWhatを考えて提案すべきでした。自分自身の付加価値を出す意味でも、達成したい目的をきちんと理解した上で手段を考え提案するのが大事だと気付いたことがきっかけの一つです。また、人事組織が大きく、採用、人事企画、HRBPなど、部門が分かれている中で「採用部は採用をしたら終わりだけど、その人が活躍して成果を出し、事業成長につながったかというところまではどうしても見えづらい」といった構造上の課題を個人的には感じていました。そういった経験から、役割それぞれが組織拡大や事業成長につながっているもので、自分の役割はその手段の一つだと感じていました。その二つの気付きから「目的達成のための手段」ということを意識するようになりました。
「この会社を成長させたい」と思えること、会社の成長のために何ができるか、どんな手段があるのかを考えることが一番好きなので、そこは自分の軸、コアな部分としてこれからも大事にしたいです。
― これからますます事業の幅も広がり組織も大きくなっていくにあたり、人事としてやらなければいけない、やっていきたいフェーズも変わっていきますね。
今は発展途中で、まだまだこれから先は長いと思っています。上場という大きな変化が会社にあり、上場の前と後では市場から会社に求められるもの、会社から各部門やメンバーに求められるものも変わります。その中でどうミッションと紐づけて会社成長させていくのか、それを組織としてどう成し遂げていくのかを考えていく難しさと面白さを感じています。そういったところも含めてなかなかできない経験ではあるので、楽しみながらやっていきたいと思っています。
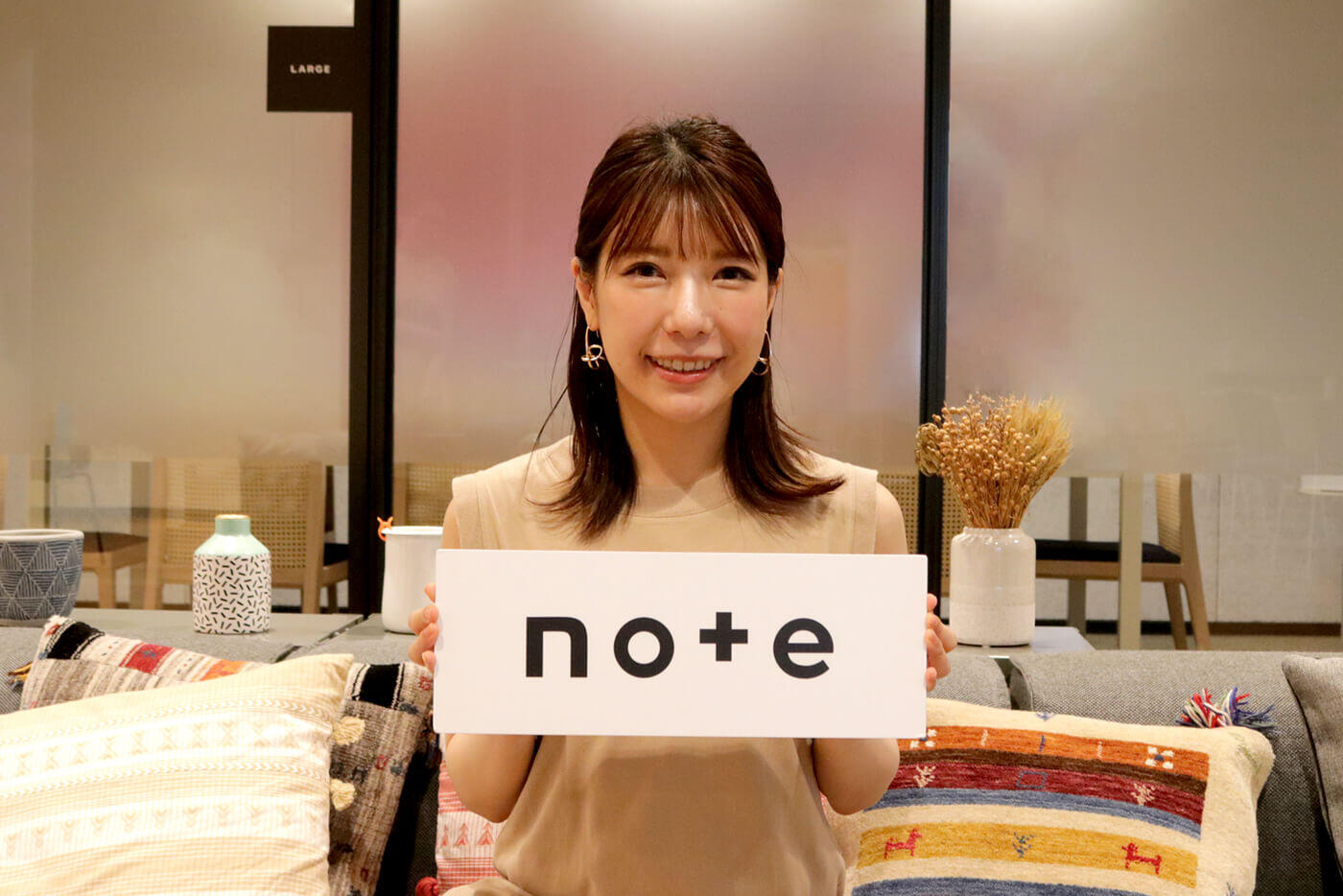
人事としても当事者としても会社を成長させたいという強い想いを持って、そのための「手段」を考え、それに徹しようとする中西さんは、大きな変化の中でも細やかなコミュニケーションや効率化にも目を向けながら奮闘されていました。
人事は「あらゆる領域の総合格闘技」でもあり、「ちょっとした日々の変化を生み出す」もの。先を見据えながら日々の小さな変化にも目を向けることで感じる人事のさまざまなやりがいや楽しさは、みなさんも共感されるのではないでしょうか。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

note株式会社
Organization Successグループ
グループ長
中西 麻子 氏
2012年、新卒としてヤフー株式会社に入社し、人事部門にてHRBPや人事企画業務に携わる。2019年5月、株式会社エブリーに入社し、マネージャーとして人事制度の企画・運用およびHRBP業務、採用業務に従事。2020年7月にnote株式会社にジョインし、2021年2月より人事チームのマネージャーに就任。その後2023年12月よりOrganization Successグループのグループ長として、人事労務領域全般を担当。
- 記事をシェアする









