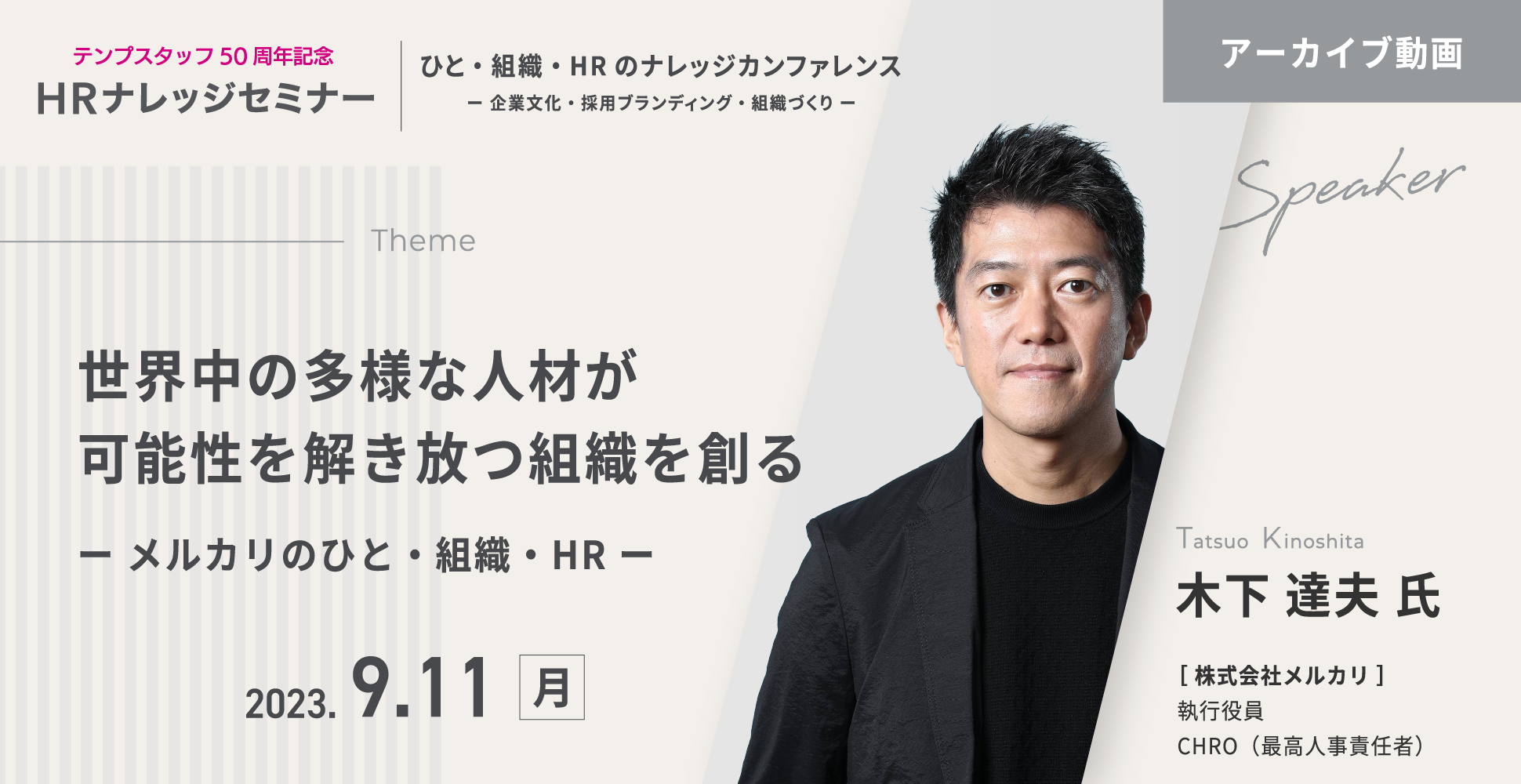HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事ライン】
メルカリ 打越氏
労務として「その人の可能性を信じ、限界に向き合う」
公開日:2024.06.28
- 記事をシェアする
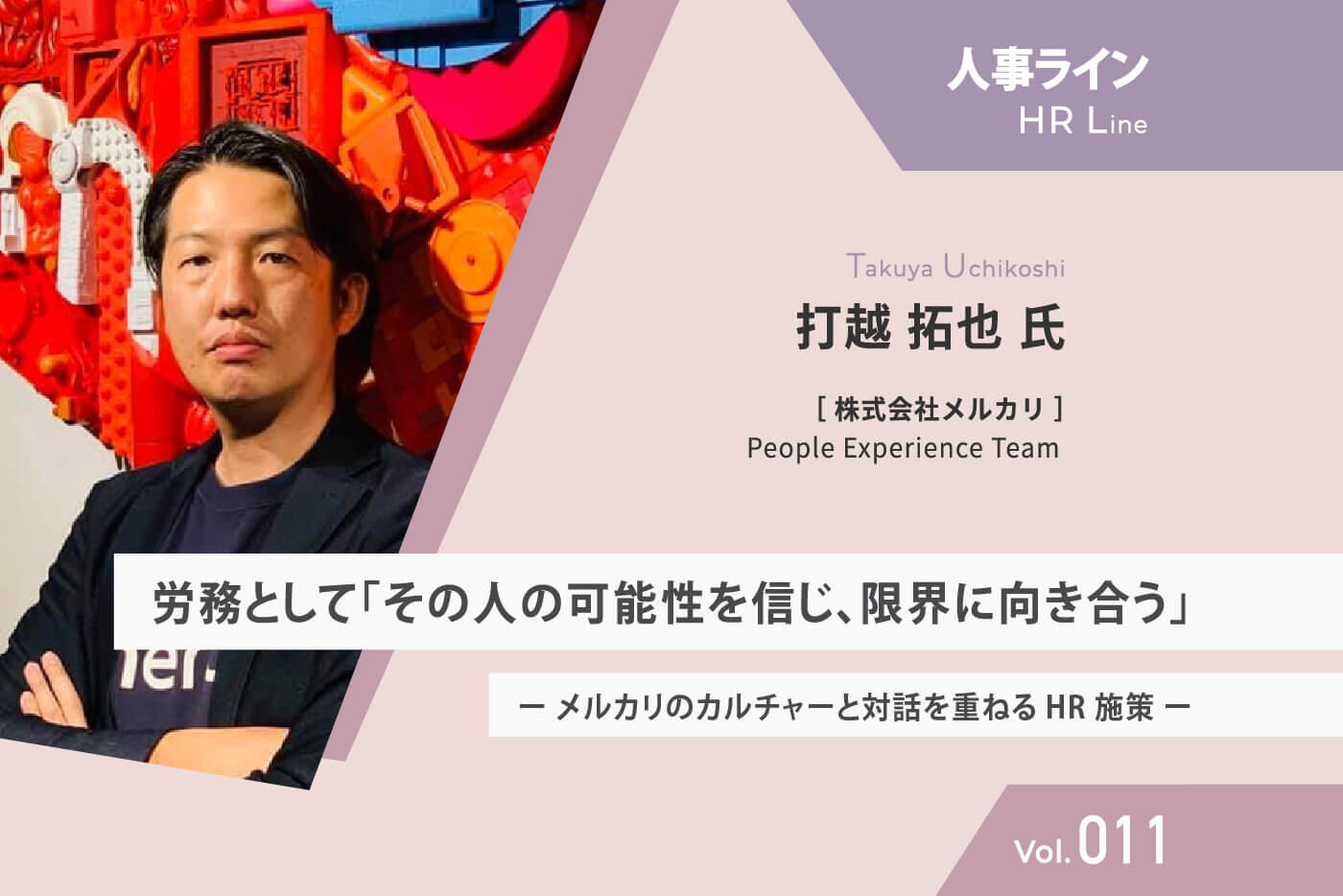
株式会社メルカリ
People Experience Team
打越 拓也 氏
「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」さまざまな企業の人事パーソンインタビュー『人事ライン』。今回は、グループ全体の労務を中心に、コロナ禍ではAfterコロナのはたらき方やカルチャーに関するプロジェクトもリードされてきた、株式会社メルカリ People Experience Team打越 拓也さんです。
メルカリのカルチャーやコミュニケーション方法、人事施策の決め方や進め方をはじめ、人事や労務の役割や想いを伺いました。
― 打越さんの今までのキャリアと現在の役割を教えてください。
大学在学中に行政書士の資格を取得し、行政書士の事務所を探していたのですがなかなか見つからず、社会保険労務士と行政書士の仕事をダブルライセンスで経営している事務所に新卒で入りました。行政書士の仕事をしつつ、徐々に労務の仕事もやるようになりました。中小企業の顧問先を数十社担当する中で、いつの間にか行政書士より労務の方が得意になり、5年で一通り実務を身に付けたという想いがありました。
その頃、顧問先の経営者の方に異業種交流会に誘われたことがきっかけで、ITスタートアップの経営者と話す機会が増え、個人的に相談をいただく機会も増えていきました。その人たちの熱量やそこではたらく社員の熱気などを感じていくうちに「数十社の顧問先の労務をやるよりは、一社のためだけに知識や経験を使いたい」と思うようになりました。また、事業会社の人事には採用、評価、組織開発、教育などがあることを知り、士業としての労務ではなく、事業会社の人事を経験したいという想いを持ちました。
そこから100人くらいの規模のITのスタートアップに人事担当として転職し、労務だけではなく、採用などを含め人事を一通り経験しました。第二創業期のタイミングだったこともあり、「自分たちのあるべき姿は何なのだろう」「どういった人が評価されるべきなのだろうか」「目指す組織と現状の組織との差分は何だろう。それを埋めるためには」という点を議論する中で組織開発を経験し、それを評価制度に落とし込み、運用も経験しました。その後、他社にM&Aされるのを期に転職をしましたが、その後も労務を軸にしながらも、その会社の規模に応じて評価制度や組織開発も担当しつつ、現在に至ります。
メルカリには2018年に入社し、現在6年目になります。入社以来、グループ全体の労務課題への対応とそこから発生する個別の労務課題の対応をしています。
メルカリではPeople & Cultureという組織があり、主にそこにHRが所属しています。採用、評価、労務、組織開発、HRBPなどのチームがあり、私がいるのはPeople Experience teamで、評価や労務などのCoE(センターオブエクセレンス)の機能があります。
コロナ禍では、People Experience teamがAfterコロナのはたらき方やカルチャーに関するプロジェクトを持っており、私も担当を持ちました。はたらき方については、個人と組織のパフォーマンスおよびバリューがもっとも発揮しやすいワークスタイル(働く場所、住む場所、働く時間)を自ら選択できる制度「YOUR CHOICE」のプロジェクトを担当しました。また、コロナ禍で人の価値観が大きく変わったタイミングでもあったので、メルカリが大事にしたいカルチャーを改めて議論するために「Culture Doc」というカルチャーを言語化したドキュメントをアップデートするプロジェクトのリードも担当しました。メルカリの拡大に応じて、現在では組織開発やカルチャーを担当するチームもでき、以前People Experience Teamが担っていた部分を、今は別のチームが持っているものもあります。
コロナ前までは、メルカリは「集まったとき、そこに生じる熱量を感じながらスピード感を持ってやっていこう」という、出社中心の会社でした。それがコロナ禍により感染拡大を防ぐために、ある意味で半強制的にリモートの会社になりました。そのような中で「YOUR CHOICE」は、メルカリのアフターコロナのはたらき方をどうしていくかというプロジェクトになります。はたらき方という抽象度が高い課題に対して、多くの従業員がリモートでも問題なく仕事ができていると実感していたため、「コロナ後もリモートワークをしたい」「リモートワークを利用し地方に移住したい」「日本ではなく海外に住みながらはたらきたい」「色々な場所に移り住みながら旅するようにはたらきたい」「バケーションしながらはたらきたい」など、本当にいろいろな意見をもらいました。
― それぞれが異なる時間や場所で仕事をする中で、チーム内でのコミュニケーションで工夫していることはありますか。

今年の3月に東京から地元の福島県に引越しをしました。「YOUR CHOICE」ができたときから、いずれは福島県にUターンしたいと考えていたのですが、子どもが小学校に入学するこのタイミングで引越をしました。私がいるチームも関東以外に住んでいる人が何人かいます。オフライン・オンライン含めさまざまな環境ではたらいているので、新しくメンバーが入ったときなどは「Workstyle Sync(お互いの働き方を話し合う会)」を行ったりしています。チームメンバーのはたらく場所や時間が異なる中でも、自分たちが気持ちよくはたらくためには、お互いのワークスタイルをある程度知っておく必要があります。
ワークスタイルもずっと同じではなく変わる可能性がありますので、「自分の生産性が上がると感じる時間帯はいつか」「突発的な勤務時間の変更はありそうか」「ミーティングをするのに最適な時間帯はいつか」などをチーム内で定期的に話す機会は必要だと思います。
― グループ全体を担当されていると会社によっても、社風やさまざまな条件も違い、また海外の方も多くいらっしゃるので、まとめていくのは大変そうです。
メルカリの特徴として、対話型組織というものがあります。重要な施策や意思決定を行うときは、多様な従業員と対話をして意見を収集しながら決めていくというものです。議論のベースとなるものをつくったあとに、この対話を行います。多様性のある組織なので、いろいろな意見が出る中で、自分たちが解決したいと考えている目の前の課題、中長期的には組織や事業の成長、ミッションの達成などを考えたときに、どの意見をどのように反映させるかを考えながら進めていきます。
― 全社との対話はどのような形で行っているのでしょうか。
メルカリには「オープンドア」という文化があります。文字通りにドアを開けているよということなのですが、当時創業者の山田進太郎や経営メンバーが従業員と対話をするために、「この時間帯はこの会議室にいて扉を開けておくから、何か知りたいことや話したいことがあったら入ってきて自由に質問してほしい」と自由に話せる機会を持ったことが始まりだと聞いています。
今では「大切なことや重要なことを決めるときには対話型でやっていきたいね」というのがメルカリのカルチャーになりました。コロナ前はオフラインで実施していたのですが、コロナを期に今はオンラインで実施しています。どのように実施するかというと、何かの施策に対して従業員と対話をする場合は「この日のこの時間帯にオンラインミーティングでこの施策案について、その背景含め説明を行います。みなさんの意見を聞きたいのでぜひご参加ください」というように、まずはSlackでオープンドアの告知を行います。当日は、前半の30分は人事から制度概要の説明を行い、後半の30分は参加者から質問を受け付けそれに対して回答していきます。この後半30分はひたすら対話をし「この点は考慮されているのですか」「法的にはどういった整理になっていますか」「経営との議論はどのようなものがあったのですか」「私はこの点にこういった内容を盛り込んで欲しいと考えています」など、多くの質問や意見に一つひとつ答えていくという仕組みを取っています。
オープンドアは誰でも参加できますが、全社で行う前にマネージャーと踏み込んだ意見交換が必要な場合もあるので、先にマネージャーのみに実施する場合もあります。また、メルカリは約25%の従業員が外国籍のため、施策の内容によっては日本語と英語の会をわけて実施もしています。わけずに同時通訳を使用する場合もありますが、わけて実施した方がそれぞれの言語で活発な意見交換が行われる印象ですね。大きな施策となると日本語と英語の回をそれぞれ5回ずつ実施したこともあります。
なるべく多くの人の意見を集約できるように、開催時間帯の設定なども気を付けています。はたらき方によっては朝や遅い時間は参加できないなどもあるため、さまざまな人が参加できるように可能な限り曜日や時間帯をバラバラに設定するようにしています。
他にももっとライトに「この制度についてわからないことがある人は自由にご参加ください」とか「このようなことをやりたいのですが、カジュアルに意見交換させてください」など、多くのオープンドアが開催されています。
― 今まで経験した企業とはどのような点が違いますか。
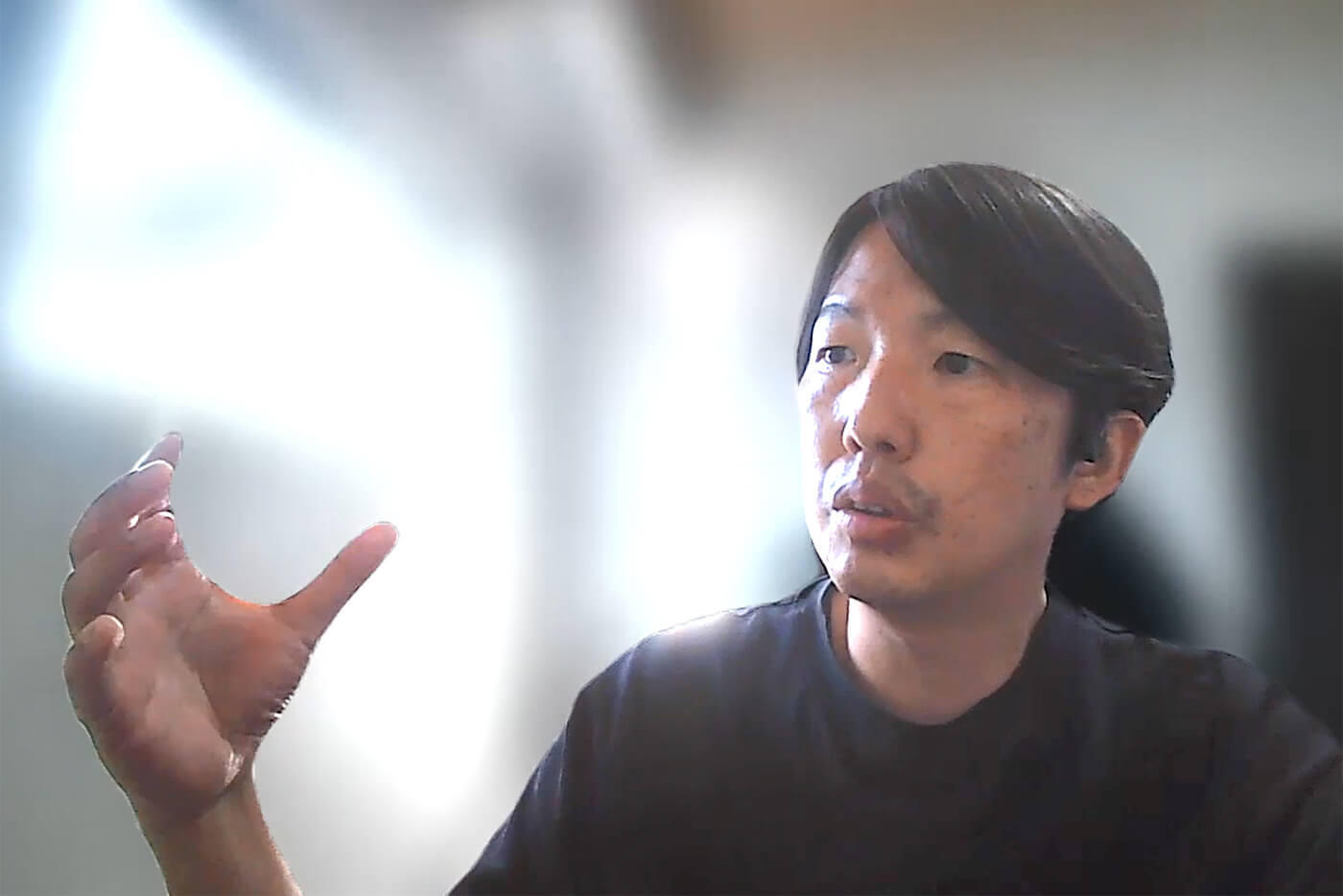
メルカリに入る前は、比較的小規模なスタートアップやベンチャーにいて、人事領域においても代表の意志や意向が非常に強く、トップダウンで決めるというような環境が長かったですね。
メルカリに入社をし、物事をつくるにあたり、ここまで社内で対話や意見の収集をするやり方は今まで経験したことがなかったので、対話の矢面に立つという意味では大変さを感じる面はあります。しかし、オープンドアを通して多様な意見に触れ、施策に反映することで、よりよい施策ができあがったという実感を持っているので、対話をすることは非常に重要だと思います。
また、施策が決定する前に意見を収集することで、組織と人事の間に信頼関係が構築されているように感じています。いつの間にか知らないところで議論され、決定事項が降りてくるのではなく、「施策や制度をつくる段階で、All for Oneに広く従業員の意見を吸いあげる仕組みと風土がある」ことが人事への信頼につながると思っています。人事と従業員との信頼関係を構築するという意味でも、対話型組織というのは大きな意味があると思っています。
― 他の企業の方に「どうしたらそのようなことができますか?うちでは無理そうです」と聞かれることも多いのではないでしょうか。
言われることはありますが、どの企業でも対話型組織の要素を入れることは可能だと思います。急に始めてもサプライズになってしまうので、まずは「なぜ対話をするのか」ということの言語化が必要だと思います。メルカリでは「カルチャードック」という形でメルカリのカルチャーを言語化しています。自社で大切にしたいことを言語化し、その中で対話の大切さも言語化して組織に伝えていくことがまず必要だと思います。
― 逆に、他社のHRの方に聞いてみたいことはありますか。
「人事観」を聞いてみたいです。私は「可能性を信じるとともに人の限界にも向き合う」というのが人事観なのですが、労務を軸にやってきた要素が根強く出ていると思います。人事の職種はいろいろあるので、それぞれがどのような人事観を持っているのかというのは、率直に興味があり、聞いてみたいです。
― 打越さんはこれまで労務を中心にHRのキャリアを重ねてこられましたが、労務のどのようなところに魅力ややりがいを感じますか。
労務の仕事は大変だなと思う反面、大きな魅力を感じています。労務はいろいろな人の想いと向き合う仕事です。ときにはその人の感情の負の部分や悩みに触れたり、人生の大きな岐路に立ち会ったり、その人の限界と向き合うこともあります。労務としてそういったものに向き合う中で無力さを感じることもありますが、その人の人生が開けたと感じるときがあり、その時には「ああ、労務をやっていてよかったな」といつも感じます。
また、今後も労務の仕事をしていく中で、「労使自治」(自社にとっての望ましい職場環境のあり方を労使が対話をしながら作り上げていく)というテーマに興味を持っています。メルカリの事業と組織の両輪が噛み合っている状況とはどういった状況なのか。今は対話型組織が正解なのかもしれませんが、企業によっては労働組合が情報を集約して会社と対話をするという形もあります。メルカリも組織のフェーズに応じて、労使自治の在り方は変化していくと思います。その中で変わらない部分と変わる部分が当然出てくると思うので、今後も労務としてその変化とも向き合っていきたいと考えています。
「労務はいろいろな人の想いと向き合う仕事。ときにはその人の感情の負の部分や悩みに触れたり、人生の大きな岐路に立ち会ったり、その人の限界と向き合うこともある」。労務という仕事に対しての打越さんの考えや想いがこの言葉に詰まっていて、深い気持ちが伝わってきました。さまざまな声を聞きながら、事業、組織、一人ひとりのことを、広い視野で考え、向き合ってこられた打越さんは、これからも変わっていく「労使自治」の在り方と共に、真摯に人と向き合い続けていかれるのだと思います。
労務とは何か、労務という仕事の魅力や可能性についてたくさんのことを知ることができたインタビューでした。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

株式会社メルカリ
People Experience Team
打越 拓也 氏
新卒で社労士事務所に入所後、ソーシャルゲーム業界のベンチャー企業にて、労務機能の立ち上げや第二創業期の組織開発、コーポレート部門のマネジメントに従事。2018年に株式会社メルカリに入社しグループ全体の労務案件を担当。コロナ禍にはAfterコロナのワークスタイルを議論するYOUR CHOICE PJ、カルチャーの浸透PJ、職域接種PJにも従事。
- 記事をシェアする