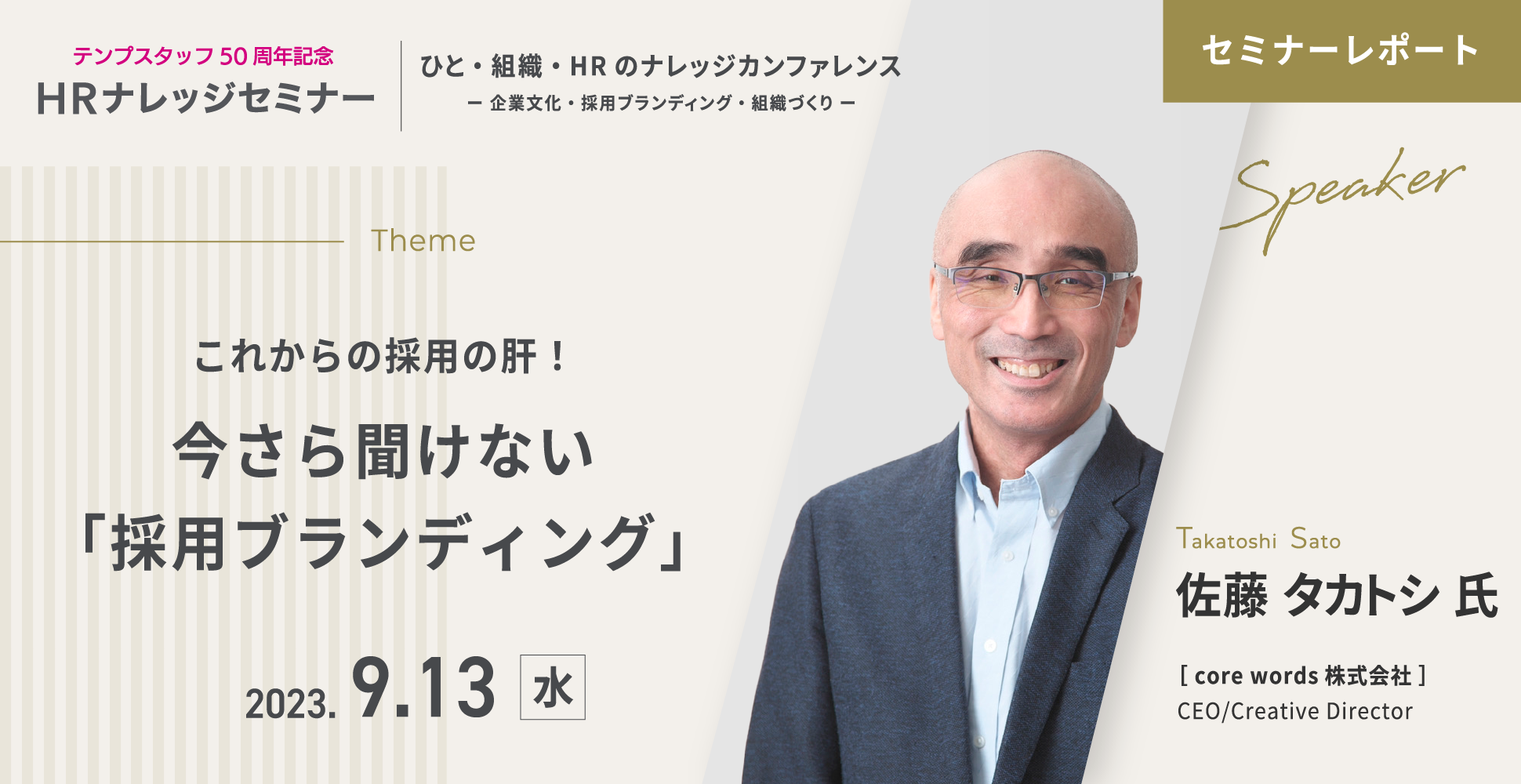HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【人事ライン】
セールスフォース 宮崎氏
給与・福利厚生は人の行動やカルチャーを変える
公開日:2024.05.31
- 記事をシェアする
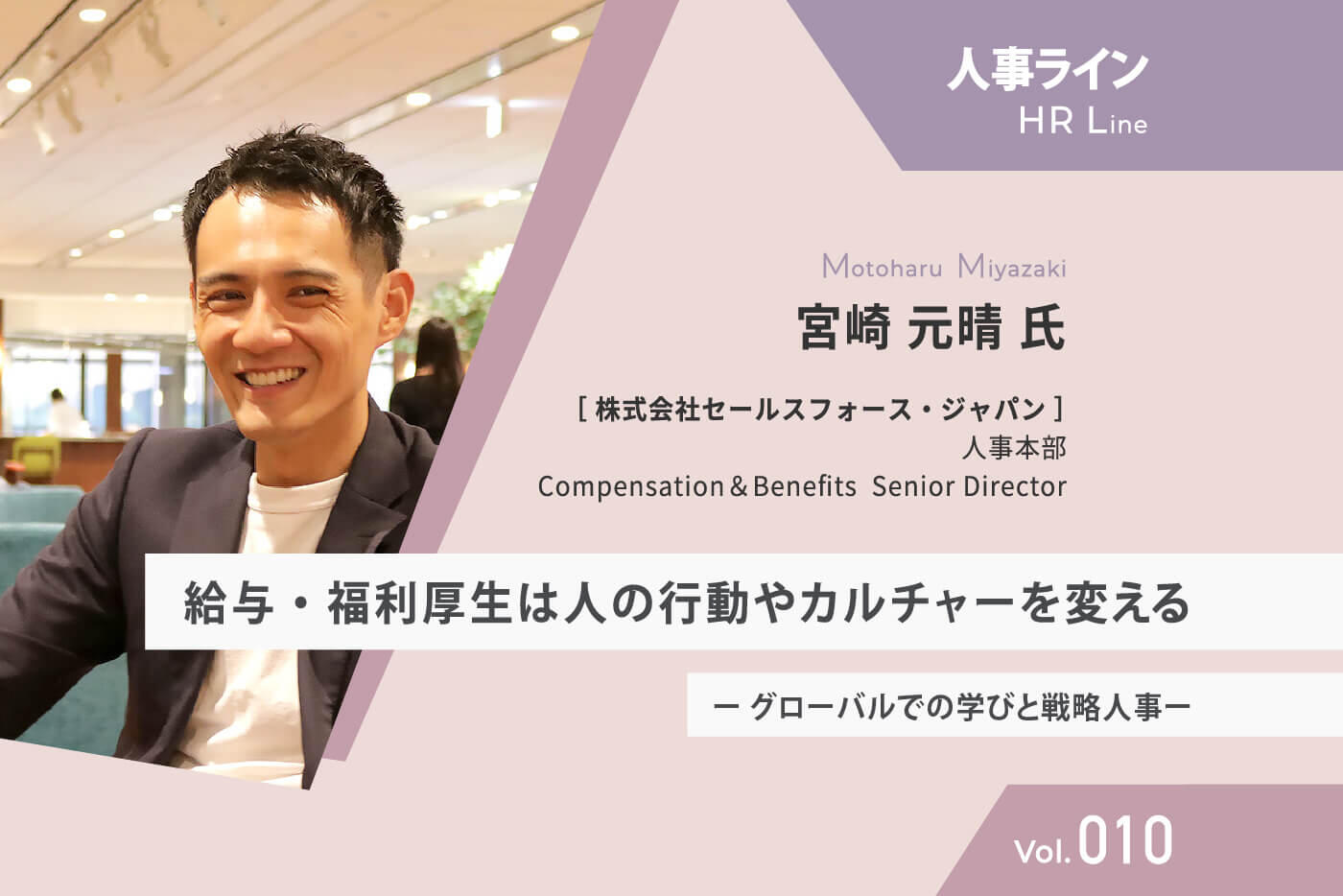
株式会社セールスフォース・ジャパン
人事本部
Compensation&Benefits
Senior Director
宮崎 元晴 氏
「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」ちょっと知りたい、知っておきたいさまざまな企業の人事インタビュー『人事ライン』。
今回は、グローバルでさまざまな国の給与・福利厚生をはじめ、ガバナンス、コンプライアンスなど、幅広い分野で活躍されている株式会社セールスフォース・ジャパン 人事本部 Compensation&Benefits Senior Director 宮崎 元晴さんです。
給与・福利厚生担当としてできること、グローバルならではのやりがいや、セールスフォースのカルチャーや従業員の自律、コミュニケーションなどについて伺いました。
― セールスフォースさんのかわいいキャラクターがオフィスの入り口から、廊下や壁、部屋のクッションからカフェのコップまで、さまざまなところで目に触れますね。
これらは私たちのキャラクターなんですよ。オフィスに置いてあるものや、コップとかクッションにもイラストが書いてありますし、フリーで食べられるキャンディーの絵など、さまざまなところで目に触れます。例えば、このフロアはフリースペースで、カフェがあったり、シェフが作ったフィンガーフードを自由にいつでも食べられたり、さまざまな打ち合わせが可能です。いたるところにセールスフォースを体現するデザインがあり、最上階のOhana Floorでは従業員の家族を招くこともできます。Ohanaは家族を意味するハワイの言葉であり、Salesforceのすべての従業員、パートナー様、お客様の絆を表しています。Ohana Floorは皆さまとゲストの方々の絆を深める場で、セールスフォースのカルチャーを体現できるフロアとなっています。カルチャーを浸透させていくことは会社全体で取り組む必要があり、いろいろな方法で進めていますが、こういったオフィスのデザインや体験もその一つです。また、人事としても社内に会社のメッセージをいかにして打ち出していくのか、カルチャーを浸透させていくか、また従業員が会社のことをどのように思っているのかということをとても大事にしています。
セールスフォースは、従業員が同じ方向を向いていて、価値観を共有しているということが、大きな特徴だと思います。そのため、セールスフォースのコアバリューである「信頼」「カスタマーサクセス」「イノベーション」「平等」「サスティナビリティ」の5つは従業員の価値観にもマッチし、しっかり伝わるし浸透していくんです。会社が大きくなるとさまざまな思想や考え方を持つ人が増えるので、メッセージが浸透しにくくなると思うのですが、価値観や方向性が共有されているというベースが整っていると、それでも浸透していきます。
人事施策だけではなく、オフィススペースで視覚から入ってくる情報や従業員同士のかかわり方などブランドや価値観をさまざまな形で社内に浸透させていくということは、大切なことだと思います。
― 宮崎さんのこれまでのキャリアと現在のお仕事を教えてください。
今までずっと人事畑で、セールスフォースが二社目となります。母親も祖父も人事でしたので、人事家系ですね。子どものころから、家で仕事の話は聞いていましたが、その当時は人事といっても分からないですから、いろいろな人と接して仲良くしていてすごいなとか、そういう感じでしたね。でも、就職、キャリアを考える時期になった時に、自然にイメージが湧く仕事は人事で、そういう仕事をしてみたいと思ったんです。それで人事で採用している会社を見つけ、外資の消費財メーカーの会社に入社し、人事で事業部人事、工場人事や採用を担当していました。そして、採用を担当する中でかなわないと思った会社がセールスフォースでした。どうしてかなわないのだろうといろいろ調べてみたら、給与・福利厚生がとても充実しているらしい。その仕事ができるのだったらやってみたいなと思ったのがきっかけでセールスフォースに転職し、今4年が経ちました。
入社後は日本・韓国の給与福利厚生を1年担当し、現在は、日本・韓国の給与福利厚生の担当に加え、Global Total Rewards, Enablement & Successチームを統括しています。給与・福利厚生の組織としては、私は戦略的な部分を主に見ているのですが、実務は担当のチームが別にあります。給与も実際の支払いに関する実務を担当するチームが行っていて、連携しながら業務を行っています。ものすごくアドミン業務も多いので、会社の戦略を支えるための仕組み作りなどにフォーカスするために、なるべくチームを分け注力できる体制を作っています。他にも人事にはさまざまなチームがあり、組織付きの人事、日本拠点全体を見ている人事などがあります。彼らと話しながら日本の今後の戦略、それこそ「採用をどれくらい予定していて何を成果としていくのか」「どんな職種を採用していくのか」「どのようなペルソナなのか」などを聞きます。それに対して私たちの給与や福利厚生が合うのか合わないかを見て、もし合わないのであればそこを変える、ということを行っています。
また、セールスフォースは世界の拠点エリアを分けて、それぞれをリージョン(地域・範囲)と呼んでいますが、AMERの北米リージョン、LATAMの中南米のリージョン、EMEAというヨーロッパのリージョン、APACのリージョン、日本韓国のJapan/Koreaリージョンに分かれています。その中で日本では私はJapan/Koreaの給与福利厚生を主に担当しています。
また、Japan/Koreaリージョンの給与・福利厚生と併せて、グローバル(すべてのリージョン)の給与福利厚生のガバナンス、リージョンをまたいで円滑にオペレーションが進んでいるかを監視・監督するチームを統括しています。ヨーロッパでも大きなチームを持っているので頻繁に足を運び、ヨーロッパのチームとつながりながら、日本と韓国のことも対応しています。
さまざまな地域を担当しており、ヨーロッパの休暇制度が特に複雑なため、直接担当しています。ヨーロッパの休暇制度ではさまざまな国の休暇制度を担当しなければならないため、例えばデンマークの休暇制度なども担当で、デンマークの休暇制度のいろいろなシステムや仕組み、法律的な部分などを踏まえた検討、そのようなものを日々調べたり考えたりしています。また、今戦闘が起きているイスラエル、ハマスにおいても、特別休暇を与えるとなった場合、イスラエルの休暇制度を踏まえてどのようにして与えるかということを判断して決めなくてはならない。そのような「この知識っていつ使うのだろう」というようなことを思いながら、さまざまな国の制度や慣習なども日々勉強しています。
― 日本と他国の共通点や違いはありますか。また、グローバルならではの調整ごとなどもあるのではないでしょうか。

ファンファクト(ちょっと意外な楽しい情報、面白い事実)みたいなものとしては、世界中のセールスフォースでは採用基準が統一され、どこのセールスフォースのオフィスといっても同じ、感じているバリューも一緒。そういうバリューや体現するもの、譲れない部分というのは常に一緒、スタンダードにしています。そのようなこともあり、社内では、国が違っても根本的な部分は結構似ているのかなと思っています。正直ほかの国のオフィスにいるときに雰囲気が一緒なので、どの国にいるか忘れたりします。
とはいえ異なる部分ももちろんあって、その国の独自さがありながらもいかに融合させていくのかということは、人事にかかっているのかなと思っています。融合させなければいけない部分と活かさなければいけない部分の両方がありますから、葛藤します。融合といえばきれいな言葉ですけれども、その過程では常に交渉をしていて、グローバルから来るものを常にプッシュバックしたり。とはいえ、「これは日本に合わないから」と全部言っていたら離れすぎてしまう。そのバランスを見極めながら「ここは譲って、ここは譲らない」みたいなことを一つずつやっています。
― 幅広く、戦略的な部分を担っていらっしゃいますが、宮崎さんは人事をどのような役割と捉えていますか。
すごくベタなのですが、人事はビジネスリーダーだと思います。そのやり方が人を通した成果を出すだけではなくて、常に会社の戦略と会社の方向性をいかにして支えていくのか実現させていくのか。会社の方針とか方向性を一緒に話して作り上げていくパートナー=ビジネスリーダーなのではないかと。人事は決してバックオフィスじゃない。私たち人事は経営における一つの大きな、重要な部門であると思っています。
― 給与・福利厚生のやりがいは、どのようなところにあると思いますか。
給与・福利厚生という仕事は、非常に面白いことがたくさんあります。人の行動やカルチャーを変えようと思うときに、一番目に出てくるのが給与と福利厚生で、それを変えればカルチャーが変わるのではないかと個人的に思っています。
前職では工場を持っている会社だったのですが、工場の従業員の行動を変えようと思ったら、給与制度を変えると目に見えて変わりました。例えば、工場でミスを防ぐことを第一とした評価や給与の仕組みを、スキルやさまざまな資格を取れば給与が上がる仕組みに変えると、すごく勉強して自己啓発していってカルチャーが一気に変わるんです。福利厚生も同じように、仕組みや制度を変えることによって人の行動は大きく変わる。カルチャーに触れ、変えることができることはこの仕事の大きなやりがいです。さまざまな国のカルチャーのことを知ることによって、いろいろなやり方や考え方に触れ、学べることも、とても面白いところです。
また、給与・福利厚生は会社の戦略に合致するものです。例えば女性活躍を推進しよういう時も、福利厚生を整えていかないと女性を採用してもすぐ辞めてしまうと思います。女性の採用、活躍を推進していこうとしたときに「じゃあ給与や福利厚生で何ができるんだろう」といろいろ考えます。「産休・育休は2年まで休めるけれどもその間の収入は相当下がるので、そうしたら長く休職したくない。子育てしにくいよね」となり、最近セールスフォースでは「26週間は給与を100%会社が払います。給与のことを考えずにその間は子育てに専念して、帰ってきて力を発揮してほしい」としました。そういった制度があることで安心して休職でき、復帰した後のモチベーションも非常に高くなり、女性活躍を推進していこうという会社の戦略に合致していくんですね。
― 苦労されている部分や難しい部分はどういったところでしょうか。
苦労している部分としては「うまいバランスを探す」ということですかね。例えば、不妊治療の福利厚生を提供しているのですが、サポートが充実しています。治療に10年かかるか1年かかるのか期間がわからない中で「治療している間合計で400万円まで治療費用を補助します」という制度です。しかし主体的に行動するといっても、どんなものでも従業員が“治療”と称して申請してしまうのも、デリケートな問題ではありますが、少し違うのではないかと。人によりさまざまであることは前提として、効果がある不妊治療の先駆的な方法や、その人に合った治療はどのようなものがあるのかということのサポートも必要なのではなのではないか。そこをフリーにして主体的にというのは、制度としては乱暴なのではないか…そこの間を見極めるのが難しい部分で、苦労しています。
この例では、最初は「不妊に関するものはなんでも費用補助します」とフリーにしてみたのですが、本人としては意味のあるものであっても、客観的にそれが治療と呼べるものなのかというようなものも含まれてきてしまいました。従業員が主体的に行動して費用の補助を申請する、でも客観的に意義のある制度にする、その間を見極めるために次に投入したのが「400万円まで提供します。併せて、パーソナルなガイドを渡します」というものでした。制度を使いたいと申請が来たら、専門のコンサルタントが「どのような治療をしたいのか」「なぜ治療したいのか」「どれくらいの時間がかけられるのか」というようなことをヒアリングします。そして「それであれば、日本においてはこういうクリニックでこのような効果が実証されていますが、どうですか」というように、一つずつサポートをしていくことにしました。パーソナルにコンシェルジュ的な人を提供して、うまく個人の主体性と客観的に意義のある制度にすることをサポートしていく部分を合わせて融合させています。
このような、バランスを考えることはとても難しいですね。最初は主体的にと比較的フリーにしても、ウォッチしながら、制度の内容を少し追加したり、変更したりしながら、ブラッシュアップしていきます。従業員に活躍してもらうための制度を作っていくのは事業戦略あってのことですので「従業員はこれを求めているけれども、本当に事業に反映されるのか?」という問いもあって、そこが難しいところだなと思います。個人のニーズと会社の戦略の交点を見つけていかければならないと思っています。
一度作った制度はそのままということではなく、常に見直してスピード感を持って変えていきます。それはソフトウェアの会社であることが大きいのかもしれないですが、常にアジャイルに動いて改善していくことがスタンダードです。
― たくさんの人とコミュニケーションをとることや、従業員の皆さんの状況を把握することが必要になってくると思います。どのような手段、工夫をされていますか。
私たちの製品である「Slack」というツールを使い、コミュニケーションをとっています。さまざまなチャンネルがあり、そこで日々たくさんのやり取りをしています。「こういうニーズがあるから、こんなことができないか」と相談がきたり、私たちから、業者さんが当社の商品をどれくらい使っているのか調べるとか、日々さまざまなやり取りをしてコミュニケーションをしています。もちろん経営層やファイナンス部門とも、そこで情報を得たり、意見交換をしています。
その時に起こりうる問題として、その話題にとって共有すべき重要な人が入っていなかったり、うまくコミュニケーションがとれないということも発生します。そのようなことを防ぐために、まずは、興味があるか、見るか見ないかは本人次第で全員が見られる状態にしています。その上で直接関連し見てもらいたい人には、その個人にタグ付けをして気付いてもらえるようにしていたり、全員に重要なものであれば全員のタグ付けをするような仕組みで行っています。
― Slack以外に従業員の声をキャッチアップするものはありますか?
従業員にサーベイを多く行っています。「グレートインサイトサーベイ」という、従業員の今の満足度や状況、どのようなことを思っているのかなど、たくさんの質問を通して把握するための大きなサーベイで、年に一回行っているものです。それ以外に「パルスサーベイ」という福利厚生に関する独自のサーベイを行っており、満足度やどのような福利厚生を入れたいのか、何を無くして何を追加したいかなどの質問をして従業員の声を定期的に拾っています。
その他には、「Equality Group」と呼んでいる従業員グループがあるのですが、そこからもたくさんの声が集まってきます。例えば「Parents and Family」という親になった人たちのグループや、「Women's Network」という女性のネットワークのグループがあったり、「Outforce」というLGBTQの方々のグループや環境問題のグループなどいろいろなグループがあります。彼らはよく会合やミーティングを開いているのですが、そこから私たちに対し「女性活躍のこういうものが足りないと思うので、何か考えてくれないか」「LGBTQ+でのこういうものが今課題になっていて、ここに対して対応できないか」などの声をあげてくれるため、さまざまな声をたくさん拾うことができています。
また、国内だけでなく「リーダーシップ」という、各国のグループリーダーが集まり、経営層がスポンサーとなっているグループもあります。経営層がスポンサーに入り、しっかりそれに対して会社としてサポートしていることを示しつつ、彼らの声をしっかり受け止めて動いていくことができます。
従業員の声を吸い上げるとか拾うという仕事は、決して人事だけでできることではありません。従業員が独自で作ったグループで声を吸い上げて、それを人事に伝えてきてくれる。なぜそういう状態にできているのかというと、従業員が主体的に動いている状態だから。もっと言うと、主体的にならないと活躍やチャンスにつながらない社風であるというところもあるかもしれません。そして、従業員が主体的に動いてくれていることで、私たちは戦略的な仕事にフォーカスできています。
― 採用や教育にも自発的・自律的なカルチャーがありそうです。

どこかの部署で採用が必要となった場合は、社内外でポスティングをするのですが、社外だけでなく社内からも、たくさんの応募があります。従業員は常に募集ポジションなどを見て、自分でキャリアを作っていきます。私もメンターとして「将来的に人事行きたいが、どのようなスキルを学んでいけばいいですか」と熱心に相談され、話す機会も多いです。自分でキャリアを作っていくにあたってのサポートは、どのように本人がやりたいのかを自分で選ぶものでもあります。
メンターやコーチもいますし、新入従業員には「トレイルガイド」という「こういう風にアクセスした方がよい」などを記載したとても細かいガイドもあります。
また、採用ということでいうと、セールスフォースを卒業して戻ってきてくれる、いわゆるアルムナイは多いですね。外に出て、ここでは学べないことを学んで帰ってきてくれることは歓迎ですし、そこは本人のキャリアであり、自分のキャリアをいかにして形成していくのかというところだと思っています。
― 今までのお話を伺っていると、自発的に動けば、一人ひとりにさまざまなサポートがありますね。
おっしゃる通り、それがキーポイントなんです。基本的には従業員が主体的に動かなければいけないという考え方に基づいているので、会社側、人事側から従業員に対してプッシュすることがありません。こちらからプッシュしない分、従業員からプルがあったものに対してパワーをかけることができます。前職の時には、従業員向けにたくさんの人事系プログラムを用意していたのですが、従業員に告知したり、利用してもらうためにものすごく労力がかかっていました。そういった労力は一切かからないので、プログラムの内容では何をしなければならないのかなど、自ら動く人に対して戦略的に時間をかけることができています。それは一番最初のカルチャーの話にもつながるかもしれないですが、そのカルチャーに共感しセールスフォースのブランドイメージなども個々に入っているので、自分のキャリアに主体的に自分から動くということも前提になっています。入社の際にカルチャーフィットするかどうかというようなところと、入ってからの融合がキーになっていると思います。
そして、実際に採用の際に各部門のさまざまな要件はあるも、入った後にそれに一つずつ触れて学んでいくということのほうが、どちらかというと大きいですね。例えば、先程の不妊治療の福利厚生も「ぜひ使ってください」とプッシュすることはありません。自分が必要でしたら自分で申請し使う。何事も主体的に行動するということにつながってくるので、そういった小さなことから大きな仕事のことまで、主体的に行動することに対してはサポートしていきますよ、というのが会社側の大きな目線です。
自分から行動できる人でないと活躍もできない環境ではあるのですが、そうだということを学んでいくと、入った時には自分から行動することに躊躇していても慣れてくるとできるようになっていきます。それが一つひとつ成長につながり、マインドセットも変化してきます。
そういうことは他の地域・国の方とかだと、カルチャー的に元々言われなくてもやるのは当たり前の方たちもいたりもしますが、いろいろな人がいてその中で共通があって、融合していくことが大事だと思っています。
― 今の課題や人事として注力されているところはありますか。
経営と事業にインパクトを出すという意味では、セールスフォースの場合、多くの中途入社の従業員にいかにして活躍してもらうかということは一つのキーになっているのですが、人事としてそこはサポートできるところがたくさんあると思うので、やりがいのあるところです。また、カルチャーに染まってほしい一方で、染まりすぎてしまったら皆金太郎飴みたいになってしまう。そういうバランスを取っていくことは苦労する部分ですね。
中途入社の従業員の活躍についてはその方法に気を付けないと、変な方向に向かってしまう可能性もあるので、そのあたりをすごく意識するようにと、中途入社の従業員がよく入る部門に伝えています。コップに半分水が入っているというよくある例えなのですが、中途入社の方って、コップに水が半分ある状態で入社してきているわけです。その時に「その後水を入れるとしたらどうする?」と聞くのですが、皆さん「追加してコップがいっぱいになるまで入れます」と言うのですが、個人的にそれは不正解かなと思っています。入っている水はもう捨てて、新しく水を注ぐというのが重要です。しかし氷は絶対捨てない方がいい。氷は自分の核になる部分で、新しい水を入れた時に、冷たくなるようにしてくれる存在なんですよね。「今までの流動的な水の部分はもう捨てて構わない。だけど自分の核を絶対捨てないようにしてね」と伝えます。新しい水、すなわち「セールスフォース的なカルチャーを入れた時に、自分の核が新しく入ったものと融合して、よりよいもの、冷たいものになるようにしていけばいいと思うよ」ということをいつもアドバイスしています。新しい水をただ注ぎ足すのは前職ありきになってしまうので、前職での経験や思考を一旦捨てて、でも考え方や進歩になることは捨てないようにして欲しいです。経営層はセールスフォース的なやり方をするようになってほしい部分があると思うのですが、やりすぎてしまうと金太郎飴になってしまうので、それがうまいバランスを取らせる方法なのかなと思っています。
― セールスフォースの従業員の方は、なぜそのように自律人材になっているのでしょうか。
もちろん会社のカルチャーもありますが、人との信頼関係というものもあると思います。やはり、会社が従業員を信頼しているということが大きいのかなと思います。例えば、どれくらいはたらくのか、わざわざ「今から開始しますよ」とか「今終わりました」とか連絡してもらうわけでもありません。仕事があるのだから仕事をして、はたらく場所もカフェのほうがはかどるなと思えばカフェで仕事をしていいですし、オフィススペースで仕事をすることもできる。最終的に成果を出す認識を信頼しているため、フレキシビリティを出しています。
― フレキシビリティで自律的な反面、シビアな部分もあると思うのですが、評価制度が気になります。
まさに、そこを今検討しているところで。いわゆる「成果をはかる」というところをやっていなくて評価制度がなかったんですよ。最近、やっとその議論検討を始めているところです。評価制度はあったほうがいいのかもとか、何をもって成果とするか。今までは評価制度はないのですが、マネージャーに任せ、マネジメントラインで決めていている形でした。「自分のキャリアを築きたい」という非常に強い気持ちを持っている人たちが多いんですね。より早く昇進したいとか、プロモーションとか大きなジョブスコープが欲しいとか、そんな風に主体的にどんどん動いていく人が非常に多い。もっと売り上げを上げるとか、必ずしもすぐに給料を上げたいとかの話ではなく、“自分のやりがい”にかなりフォーカスしている人が多い環境、社風もあって、そういうスタイルが成り立っていたのかもしれません。
― 最後に、宮崎さんがこれから人事パーソンとして目指したいことを教えてください。
海外で活躍されている日本人の人事パーソンが何人かいらっしゃって、皆さん輝いていて本当に優秀な方たちなんです。ただ、人数としては他の国と比較するとまだまだ少ないので、日本の人事が海外で輝ける方法をぜひ学んでいきたいと思っています。海外に行って挑戦するという日本の方がまだ少ないので、それにチャレンジできたら。もしそれができなかったとしても、そのノウハウややり方を学んで日本に伝授していきたいです。
海外でいろいろなカルチャーの人と話して、日本人がこれからもどんどん活躍できるようになっていけたらなと。もちろん日本の中でも多様な方がいらっしゃいますが、海外の文化が違う人たちと一緒に仕事をすることで、自分で活かされることとか自分で気付けることとか、本当に大きい経験だと思います。また、グローバル化についてこれからどのようにしていくべきなのか悩まれている企業も多いと思ので、海外のノウハウや知識を身に付けて、そういうところにも役に立てたらと思っています。

セールスフォースならではのカルチャーとそこに紐づくさまざまな施策、制度、コミュニケーション、人材教育など、事例を含めてさまざまなお話をいただきました。また、中途入社の従業員にどう活躍してほしいかという、コップ中の水と氷の話もとても印象的でした。
細かな情報もキャッチし、学び、意思を持って人事を推進していく宮崎さんは、自律的・自発的なカルチャーをそのまま体現しているようで、このような方達が影響をし合って、さまざまなものを創っていく組織の様子が浮かびました。
給与・福利厚生という仕事を戦略的に進めることでの可能性とやりがい、広いグローバルの舞台で、さまざまなことをバランスを考えコミュニケーションし変化させたり融合させていくことは、給与・福利厚生やグローバルの領域ではなくても通ずるものを感じました。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
Profile

株式会社セールスフォース・ジャパン
人事本部
Compensation&Benefits
Senior Director
宮崎 元晴 氏
早稲田大学国際教養学部を卒業後、2013年にP&G Japanに入社。HRBPや工場人事、APAC地域の採用戦略などを牽引し、組織変革からHR管理まで幅広く担当。2019年にセールスフォースに転職し、現在はグローバルトータルリワードチームで業務効率促進Senior Directorとして活躍。チーム運営に関するフレームワーク提供やデータ駆動の意思決定支援に従事。給与や福利厚生プログラムの改善、新規取り組みの導入など、多岐にわたる経験を持つHRプロフェッショナル。
- 記事をシェアする