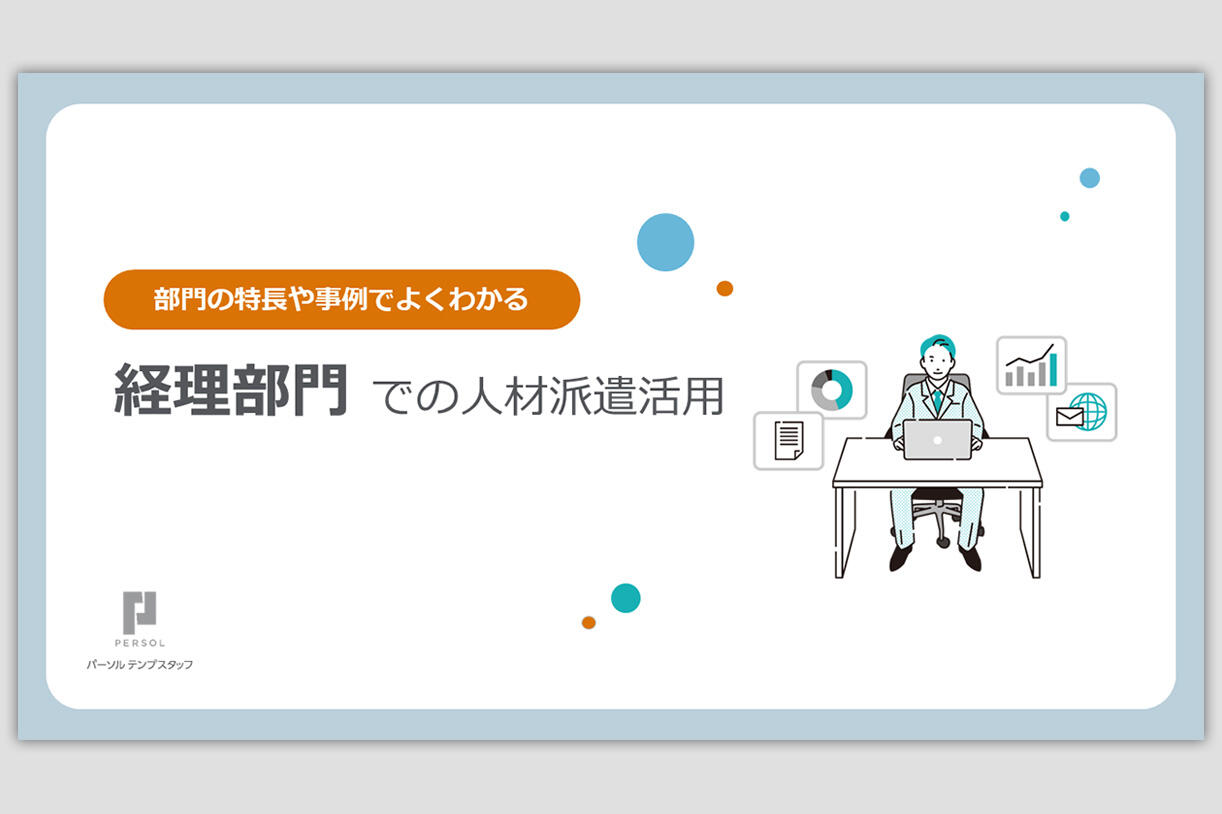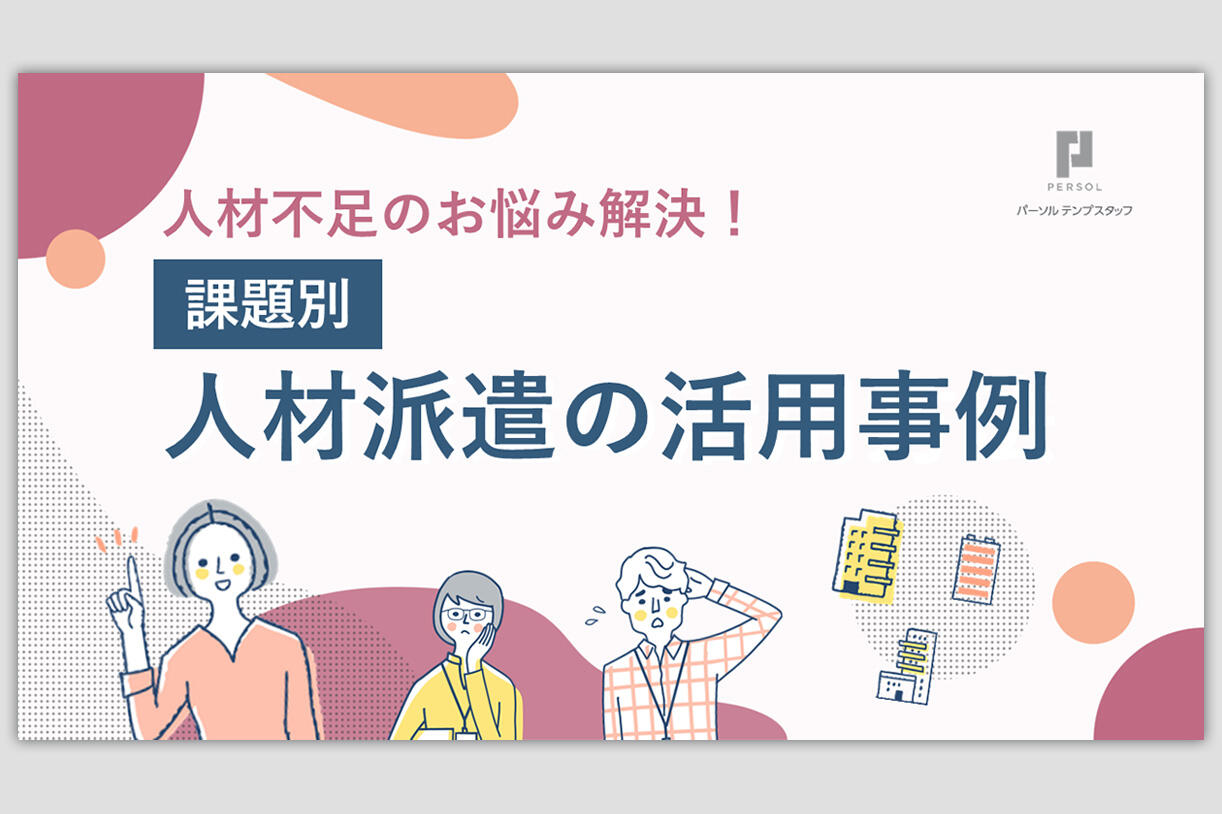HRナレッジライン
カテゴリ一覧
経理効率化までのステップとは?経理効率化の方法もご紹介
公開日:2023.05.15
- 記事をシェアする

経理業務は企業経営に欠かせない業務の一つです。経理の効率化は、どの企業にもとても重要な課題と言えるでしょう。経理の効率化が注目される理由、経理の効率化の方法とそれぞれのポイント、進める際に役立つフレームワークを詳しくご紹介します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
経理効率化の必要性
経理業務は、日々発生する業務だけでなく、月末、年末、年度末など特定の時期に発生する業務もあります。内容自体も煩雑なものが多いため、経理の効率化はどの企業も抱えている課題であると考えられます。ここでは、経理の効率化が求められる理由を解説します。
ミスの防止
経理部門では、企業のお金の流れを管理しています。経理業務上のミスは取引先企業との信頼関係が損なわれる恐れもあり、経理業務にミスは許されません。ところが、「ミスは決して許されない業務」という意識が強くなり過ぎると、今度はミスの防止を重視するあまり作業スピードが落ちます。
人手不足への対策
経理業務自体は、企業に直接利益をもたらす存在ではありません。そのため、多くの企業の経理部門は最低限の人数で運営している傾向があります。特に、中小企業などでは経理担当者が一人というのも珍しくありません。
経理業務の変化
経理部門が取り扱う業務内容は、企業の経営判断に直結しています。決算関連業務の精度が低ければ、より的確な経営判断を下すのは難しいでしょう。あるいは決算業務が遅延するようなことがあれば、タイムリーな決断はできません。こうした理由から、健全な企業経営を推進するためには経理効率化が必要とされています。
近年の傾向として、テレワークを導入する企業が増加していることも経理効率化が必要とされる要因に挙げられます。経理業務は紙媒体帳票を扱うことや業務内容の性質からテレワーク導入は難しいとされることが多く、業務効率化が求められています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
経理業務の効率化が難しい理由
経理業務の効率化は企業にとって重要な課題ですが、効率化が進んでいる企業ばかりではありません。経理業務の効率化が難しい理由は主に以下の通りです。
紙媒体での業務が多い
請求書や領収書をはじめ経理業務で扱う資料や帳簿書類は、紙媒体であることが多いです。そのため、経理業務では書類整理、押印、必要に応じて郵送作業などが発生します。
早さよりも正確性が求められる
経理業務では、金額の記入箇所や額面のミスなどに注意が必要です。経理部門が作成した書類は証憑書類として保管されます。内容に不備や間違いが発覚した場合、取引先企業との信頼関係でトラブルが生じたり、税務申告に関する内容なら加算税や延滞税が発生したりする恐れもあります。そのため経理業務では、早さよりも正確性が求められます。
経理効率化の方法
経理を効率化するための方法はいくつかあります。本記事では以下5種類を解説します。費用対効果などを考慮しながら、職場に適した方法を取り入れて経理の効率化を推進しましょう。
書類のフォーマットを統一する
使用するフォーマットを社内で統一すると、経理処理のスピードアップが期待できます。
複数の部署で異なるフォーマットを使用している場合、フォーマットごとの違いだけでなく記載方法や処理を覚える必要があります。そのため、複数の担当者で対応することによるミスが生まれやすくなります。フォーマットを統一すれば、個別に処理する必要がなくなりミスも減らせるため、経理業務にかかる時間を短縮できるでしょう。
またフォーマットの統一は、業務の属人化を防止し、誰でも適切な処理ができるなどのメリットも持ち合わせています。
ペーパーレス化を図る
経理業務で使用する帳簿書類をスキャナーなどで取り込み保存管理するペーパーレス化も、経理の効率化が期待できます。
電子帳簿保存法が改正され、請求書など原則紙媒体での保存が義務づけられている帳簿書類でも、2022年から一定の要件を満たしている場合は電子データでの保存が認められるようになりました。ペーパーレス化には、印刷代や紙代の削減、印刷した帳簿書類の保管場所の削減、保管している帳簿書類の整理整頓の手間が省けるため内容を確認したいときにすぐ発見できることなどのメリットもあります。
キャッシュレス化を図る
小口現金処理を廃止してキャッシュレス化を導入する方法もあります。キャッシュレス化は特に社員数が多い企業で効果を期待できます。
小口現金があると、出納帳管理、金庫管理、両替、補充などの業務が発生します。出納管理帳と小口現金残高が一致しなければ、原因の調査が必要です。小口現金を廃止してキャッシュレスに一本化すれば、こうした管理業務がなくなり経理効率化につながるでしょう。
ITツールを活用する
経理業務ではExcelを使用した管理が一般的でしたが、経理業務に求められる役割が変化したり、業務内容が複雑化したりしたため、Excelでは対応しきれない局面も登場しました。
ITツールを導入するには、Excelから切り替えるための事務処理が事前に必要になりますが、Excel使用時のように複数のシステムやソフトを併用する煩雑さから解消されます。
アウトソーシングを活用する
経理業務を効率よく進めるため、自社にとって負担となっている業務を洗い出して、外部の協力を求める選択肢もあります。伝票処理、税務申告、報告書の作成などの経理業務を、外部の専門業者や税理士事務所などにアウトソーシングする方法です。
給与計算や請求書の作成など、一部の業務のみアウトソーシングすることもできます。また、年末や年度末など繁忙期のみアウトソーシングを活用する方法もあります。アウトソーシングでは幅広い業務に対応していますので、自社の経理業務が抱える問題点とニーズに応じて活用しましょう。
パーソルテンプスタッフでは、アウトソーシングサービスをご提供しています。さまざまな分野で実績があり、状況に合わせたサービスのご提案が可能です。
▼パーソルテンプスタッフのアウトソーシング・BPO

アウトソーシング・BPOの活用メリットや対応業務・ご利用の流れを紹介
経理効率化までのステップ
経理効率化を実施するにあたって、いつ何を実施すればよいのか、実施内容と気をつけたいポイントを解説します。
現状の経理業務を洗い出す
現状の経理業務の全体像を把握します。具体的には、経理業務の担当者、詳細な業務内容、業務を遂行するにあたりかかった時間、その業務を実施する目的です。
現状の経理業務を洗い出すときは、経理業務に関連する一覧表を参照すると実施しやすいでしょう。例えば、決算スケジュール表や経理業務一覧表などがあれば参照します。もちろん、以下のように主要な経理業務をピックアップし一覧化して実施する方法でも問題ありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経理業務の洗い出しが完了したら、各業務の内容を分析します。業務の実施手順、業務を進めるにあたってボトルネックとなりうる要素を探し出します。
ECRSの法則で効率化できる業務を整理する
ECRSとは、業務改善を目的とした4つの視点で構成されるフレームワークです。より高い業務改善効果が狙える順番で並んでおり、それぞれのポイントを意識しながら業務を見直すことにより、改善点を明確にします。
ECRSは製造業の現場で考案されました。現在では製造業以外にも、小売業やサービス業などさまざまな業界で応用されています。また、事務職や営業職など部署を超えて業務フローを見直す際にも取り入れられているフレームワークです。
取り除く(Eliminate)
業務全体を見て、明確な目的がないまま実施している業務や、業務の意図を把握せず「なんとなくやるもの」と認識しており習慣化している業務を探します。
具体的には、必要とされていない報告書の作成、形式的に実施されている会議、本来必要とされている以上の人員配置などが該当します。実行時は明確な判断軸があると作業しやすくなります。
- 業務を実施する目的
- 業務は不可欠な工程
などを意識しましょう。
ECRSで実施する4ステップの中でEliminateが最上位に来ている理由は、検討の容易さとより高い効果を期待できる点にあります。日常業務は身近なことも相まって、見直しを図りやすいです。今まで実施していたフローとプロセスをこの機会になくすことができれば、経理業務にかかっていた時間やコストの削減を期待できます。
つなぐ(Combine)
業務効率化に向けて、個々の業務をまとめてあたらしく一つの業務にできるかどうかチェックします。例えば、業務で必要な資料はメールで一括送信して共有する、別の日時に実施していた複数の定例会議は一度にまとめて実施するなどの対応は、まさにCombineに該当します。
Combineは、細分化され過ぎた結果、工程が煩雑になっている業務を効率化することで効果が期待できます。業務そのものの目的が明確になることから、工数削減も可能です。
また、似たような業務を別々の担当者がそれぞれ実施しているケースの発見にもつながります。業務を整理してまとめ、各担当者に業務を配分します。以下を想定しながら業務を振り分けるとよいでしょう。
- 業務を効率的に進めるにあたり必要な人数
- 業務内容を考慮した結果、適任と思われる人物
複数のフローやプロセスで構成されている業務も、一度切り離してから再構築方法を検討することで、より効率的な組み合わせを見つけます。
組み替える(Rearrange)
業務内容を見直して、現状と問題点を考慮しながら業務内容自体を再構築する方法です。先ほど解説したCombineは業務をつなげるのを目的としているのに対して、Rearrangeはもう一歩踏み込んだ業務整理と考えます。
Rearrangeのメリットは、EliminateとCombineを実施しても思うように改善できなかった問題点の改善が期待できることです。
- 業務フローを精査して、着手する順番や担当者を変更する
- 業務を実施する場所や配置の変更を検討する
- 業務内容全体を精査した上で、一部の業務をアウトソースする
より広い視野から見た改善策を立案・検討できます。また、実施後の効果測定と微調整も可能です。
Rearrangeの具体的な例としては、上長による確認のタイミングの変更、複数名が別の場所から参加するオンライン会議の実施などがあります。
経理効率化を想定したRearrangeの具体例は、記帳処理や給与計算などの業務が該当します。経理業務は専門性が求められます。仮に担当者が退職するような場合は、同じように経理の知識や実務経験がある社員が業務を引き継げば問題ありません。
しかし、そうした人材を見つけられなかった場合、経理業務がストップするおそれがあります。こうしたリスクを回避するためにも、経理業務のアウトソーシングは前向きに検討してもよいでしょう。
パーソルテンプスタッフでは経理のアウトソーシングも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。詳細はこちらをご覧ください。
簡単にする(Simplify)
その業務の中で単純化できる部分を探します。ECRSで最初に実施するEliminateは業務そのものをカットできるかという観点で考えるのに対して、Simplifyでは無駄な部分をそぎ落としたり、パターン化できる要素を探し、よりシンプルにすることを目的としています。
Simplifyは、業務プロセスが固定化し、長期間にわたって同じ方法が踏襲されているケースや、共有や承認が多い業務で効果を期待できます。具体的には、使用する資料のテンプレート化、入力項目のカット、関連部門間で共有する書類の押印箇所を減らす方法などがあります。チャットツールやデータのクラウド管理も、Simplifyに該当します。
Simplifyは検証や実施に時間やコストがかかります。一時的な負担は増えますが、業務効率化やヒューマンエラー防止が期待できるため、Eliminate、Combine、Rearrange同様大切な考え方です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
経理業務を整理して、経理効率化を図る
経理効率化の必要性、経理効率化が難しいとされる理由、経理効率化の方法と具体例を解説しました。
今回解説した内容で特に重要なポイントは、以下の通りです。
- ミスの防止、人手不足対策、経理業務に求められる要素が変化したことにより、経理の効率化が求められるようになった
- 紙媒体が主流であることや、正確性が重視されるという特性から、経理業務は難しいと言われている
- 経理を効率化するには、フォーマットの統一、ペーパーレス化、キャッシュレス化、ITツール導入などの方法がある
- 経理の効率化は、複数のステップで計画的に実施するのが望ましい。現状の業務を洗い出し全体像を明確にしてから、ECRSの法則を参考にボトルネックとなっている業務への対応を考える
- 社内リソースのみで対応するのは難しい業務や日常的に発生する業務は、アウトソーシングを活用することも考える
経理担当者の負担を減らし、また健全な企業経営を推進するためにも、経理業務の全体像とボトルネックについて把握しましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
- 記事をシェアする