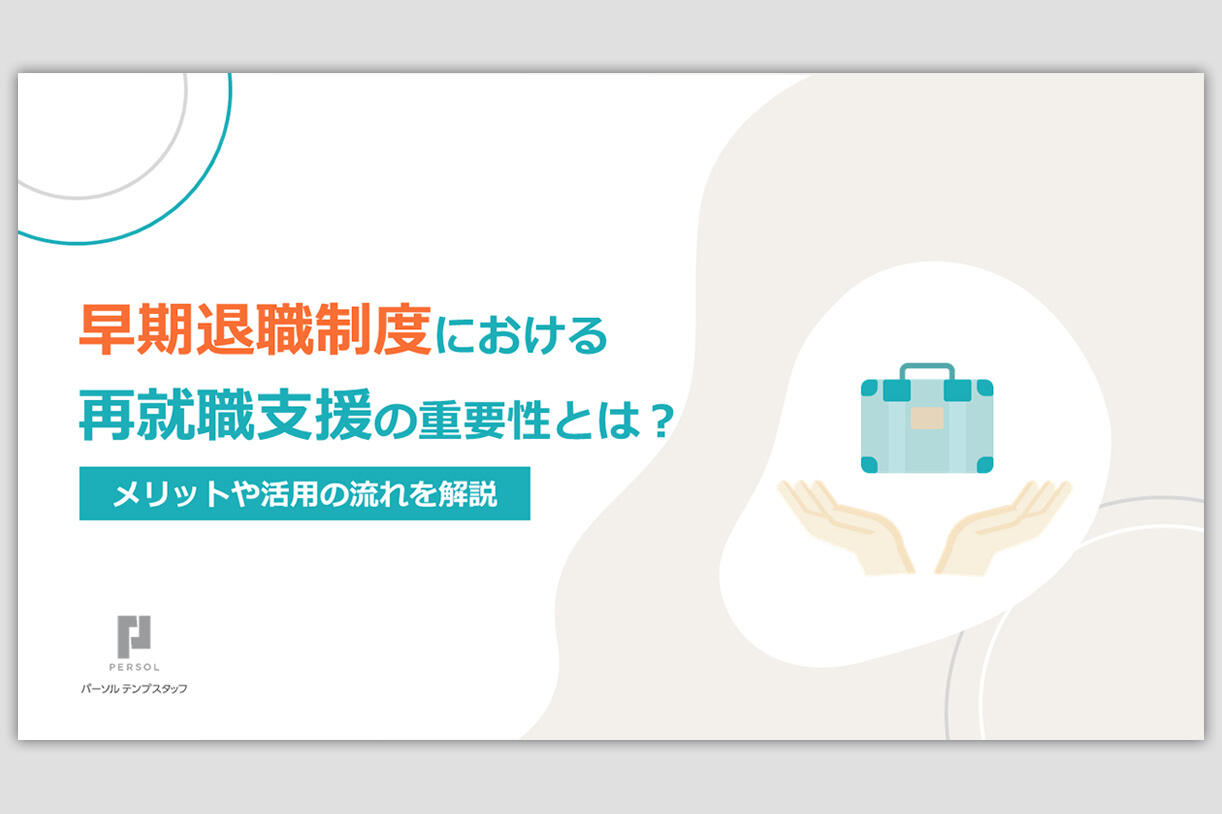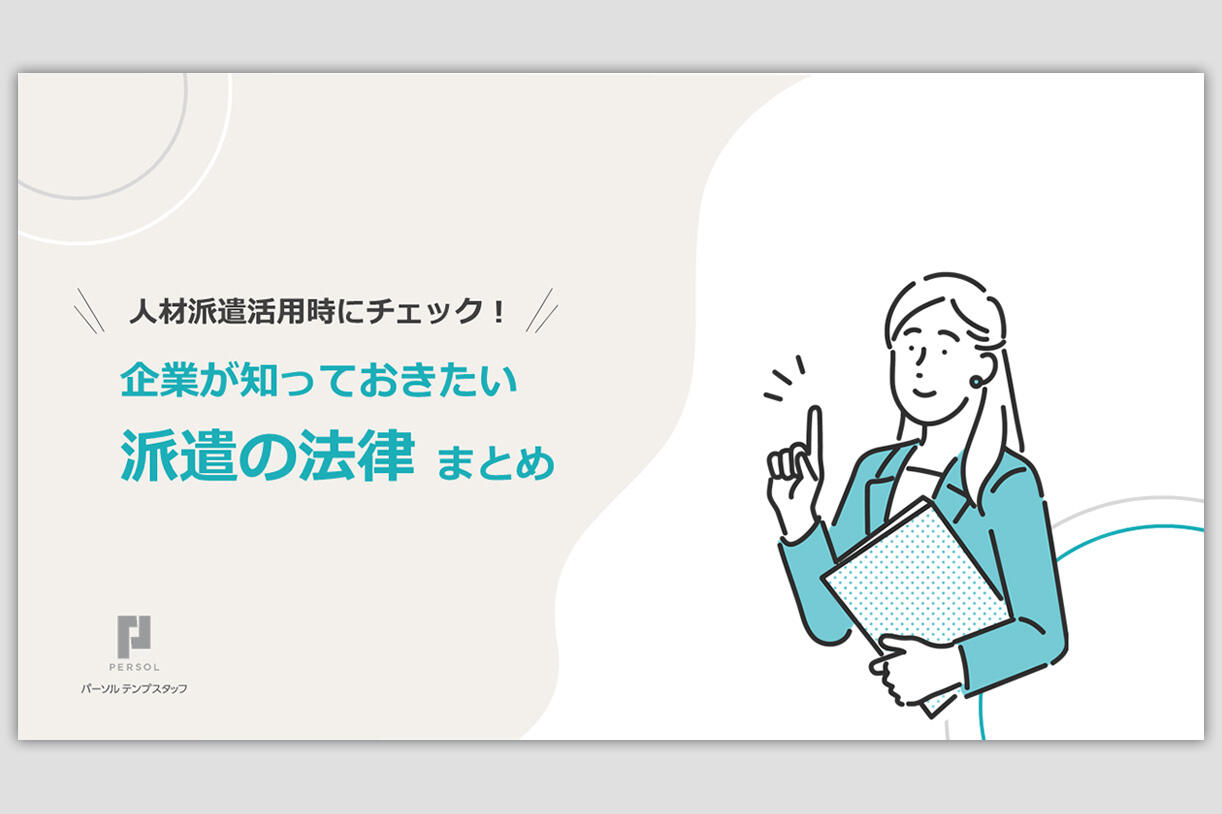HRナレッジライン
カテゴリ一覧
早期退職制度とは?企業側のメリットや留意点、実施の流れを解説
- 記事をシェアする

早期退職制度とは、定年退職よりも前に退職する機会を提供する制度です。福利厚生の一環や組織の活性化、長期的な視点での人件費の削減などを目的として早期退職制度が活用されます。
この記事では早期退職制度の意味や企業側のメリット、運用する際の留意点、実施の流れなどを解説します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
早期退職制度とは社員が定年よりも早くかつ自主的に退職するための制度
早期退職制度とは、定年前に退職を希望する社員が、自主的に退職できるようにするための制度です。一般的に退職希望者は退職金の割増しや勤務の免除、キャリアサポートなどの優遇措置が受けられます。
社員は退職を強要されることはないので、早期退職制度があったとしても定年までその会社で勤めることは可能です。
早期退職制度の目的とは?
早期退職制度は福利厚生の一環として活用されるケースが多いです。今や定年まで一社で勤める終身雇用・年功序列の時代ではなくなりつつあります。そのような中、転職・独立・開業・早期リタイヤなど、社員が自身の理想とするさまざまな人生を歩んでもらうことを目的として、早期退職制度を活用している企業が増えてきています。
また、組織の若返りや長期的な人件費の抑制を目的として早期退職制度を活用している企業もあります。
希望退職制度との違い
早期退職制度と似たような制度として、希望退職制度があります。早期退職制度は社員が自主的に退職できる制度で、希望者を恒常的に募集します。希望退職制度は期間を限定して希望者を募るという点が、早期退職制度との大きな違いです。
また、早期退職制度は福利厚生の一環として活用されることが多い一方で、希望退職制度は経営状態が悪化した際に人件費の抑制策として実施されることがあります。
退職勧奨の有無も、早期退職制度と希望退職制度の違いです。早期退職制度では退職勧奨がある場合と無い場合があります。希望退職制度では、退職勧奨があることが一般的です。
選択定年制との違い
選択定年制は60歳から65歳の間で、社員自身が定年退職する年齢を決められる制度です。早期退職制度では定年前に退職することが前提ですが、選択定年制では定年まで勤めることが前提となっています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
企業が早期退職制度を実施するメリット
企業が早期退職制度を実施するメリットには、以下のようなものがあります。
- 人員調整を円滑に進めやすくなる
- 長期的な視点では人件費を削減できる
- 若手社員のキャリア形成促進による組織の若返りを実現できる
ここでは、企業側のメリットについて解説します。
人員調整を円滑に進めやすくなる
早期退職制度では、自主的な早期退職を希望する社員を募れるため、人員調整を円滑に進められます。企業側が一方的に人員調整を進める整理解雇と比べて、社員との合意のもとでやり取りでき、トラブルを避けやすいことが早期退職制度のメリットです。
長期的な視点では人件費を削減できる
早期退職制度を実施すると、社員が定年退職するまで給与を支払う場合と比べて、トータルの人件費を抑えられます。特に、勤続年数に応じて給与が上がる企業では、長期的な視点でのコストを削減できる可能性が高いです。
若手社員のキャリア形成促進による組織の若返りを実現できる
社員の年齢に応じて昇給・昇格させる人事制度をとっている企業は多くあります。年長者が早期に退職することで、若手社員に重要ポストを任せ、昇給させられるようになり、組織の若返りを図れます。
企業が早期退職制度を実施する際の懸念点
早期退職制度にはメリットだけでなく懸念点もあるため、両方の側面を理解することが重要です。主な懸念点として、以下の項目が挙げられます。
- 生産性の低下
- 一時的なコスト増加
- 経験や実績が豊富な人材の流出
ここでは、企業が早期退職制度を実施する際の懸念点について解説します。
生産性の低下
社員が早期退職することで人材が減少していきます。特にスキルや知識が豊富な社員が早期退職すると、生産性が低下する可能性があります。早期退職前に他の社員に引継ぎを行ったとしても、同じパフォーマンスが出せるとは限りません。
早期退職制度を活用しても業務が円滑に進むか、生産性が低下しない体制が整っているかを検討することが重要です。
一時的なコスト増加
早期退職制度は、一時的にコストが上昇することになります。早期退職者には退職金を支給し、さらに個人の勤続年数や役職に応じた割増退職金を上乗せすることが一般的です。 独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表している「事業再構築と雇用に関する調査」によると、退職金の割増しを実施している企業は、早期退職制度を活用している企業の約9割です。平均値で月給に換算して15.7ヶ月分、中央値で12ヶ月分を割増しして退職金を支払っているという結果が出ています。
特に早期退職希望者が複数人いるケース、定年退職者とタイミングが重なったケースなどでは、資金繰りが悪化するリスクもあるでしょう。
早期退職制度は長期的な人件費を削減できる一方で、一時的にコストが増加する可能性もあることを念頭に置く必要があります。
経験や実績が豊富な人材の流出
全社員を対象として早期退職制度を実施すれば、経験や実績が豊富な社員も退職を希望する可能性があります。あわせて生産性が大きく低下するおそれがあります。また、退職した社員が競合他社に転職した場合や、独立・開業した場合のリスクも懸念点の一つです。
職種や年齢、勤続年数、募集人数などの条件を絞ることがリスクの軽減につながります。
早期退職制度を実施する流れ

早期退職制度を効果的に実施するには、精度の目的や対象者などを明確にした上で、社員との協議や周知を進めることが重要です。
ここでは、企業が早期退職制度を実施する際の流れについて解説します。
1.制度の目的や対象者、条件を定める
まずは、自社で早期退職制度を活用する目的を定めましょう。そして、その目的に沿って対象者や条件(職種、年齢、勤続年数など)あるいは制度の内容を決定します。
例えば、組織の若返りを図るという目的があれば、高年者が対象者となるでしょう。社員の自由なキャリア形成を目的とするのであれば、キャリアサポートや再就職先の紹介といった優遇措置を設ける進め方もあります。
目的を定めないと、対象者や条件を適切に設定できません。また、社員から「リストラするのではないか」「経営状態が悪いのではないか」などと誤解される可能性があります。
2.社員との協議・取締役会で決議する
制度の大枠が決まったら話し合いやアンケートなどで社員の意見を聞く場を設けます。早期退職制度は社員のその後の人生に大きな影響を与える仕組みです。社員の意見を取り入れることで、新たな課題や問題点の発見につながります。
なお、早期退職制度は会社法362条4項の「重要な業務執行」に該当する可能性があります。制度を開始する前には取締役会で決議を得ましょう。
3.社員に周知・説明する
早期退職制度を実施する前に社員への周知・説明を行いましょう。社内報やメールで周知する、部署ごとに部門長が通達する、説明会を開催するなど、さまざまな方法を用いて社内に浸透させる必要があります。
早期退職制度がリストラ施策と誤解されないよう、目的や内容を正確に伝え、疑問や不安を持つ社員には丁寧に対応することが大切です。
4.制度の運用を開始する
実際に制度を開始し、希望者が現れたら面談を行います。面談で話し合う内容は、退職日や退職金の支給、優遇措置などについてです。双方で認識のズレがないように話し合いを進めましょう。
また、制度を開始することで、新たな課題点が見つかる可能性もあります。PDCAを回して制度をブラッシュアップしていくことが重要です。
早期退職制度でよくある優遇措置
早期退職制度では、自発的に退職する従業員に対して優遇措置を提供することが一般的です。主な優遇措置として、以下のようなものがあります。
- 割増退職金の支払い
- 有給休暇の買い上げ
- 再就職支援の提供
それぞれの内容は以下の通りです。
割増退職金の支払い
早期退職制度では、通常の定年時よりも多くの退職金を支払うケースがよくあります。割増金額の設定方法は、全員一律や勤続年数に応じた算出など企業によってさまざまです。
経営状況や原資などに応じて、自社に合った方法で割増退職金に関するルールを設定しましょう。
有給休暇の買い上げ
早期退職制度を利用する社員が有給休暇を使い切れない場合に、企業が買い上げることもあります。あくまでも有給休暇を退職日までに使い切ることを前提として、消化が難しい場合の優遇措置として買い上げのルールを設定しておくと、柔軟な対応が可能です。
再就職支援の提供
早期退職制度を利用する社員が再就職できるような支援を提供することも、よくある優遇措置の一つです。再就職支援を提供している人材サービス企業と契約を結ぶことで、再就職先の紹介や履歴書作成、面接の練習といった支援が可能になります。
早期退職制度を活用する際に気を付けたい4つの注意点
早期退職制度を活用する際に特に気を付けたい点はこちらの4つです。
- 守秘義務を徹底する
- 社員への説明は入念に行う
- 会社の承認を必須条件とする
- 業務の引継ぎ体制を整備する
守秘義務を徹底する
早期退職に限らず、社員が退職する際には守秘義務を徹底させましょう。特に早期退職の対象となり得る中高年の社員は、会社のさまざまなノウハウや内部情報を把握している可能性があります。こうした秘密情報が競合他社に漏れることで、会社の利益が阻害されるおそれがあります。
また、社員が競合他社に就職したり、会社で得たノウハウを活用して独立・開業したりすることで、自社の不利益につながるケースもあります。守秘義務や競合避止義務については退職時にしっかりと書面で取り決めておくことが大切です。
社員への説明は入念に行う
退職金の支給額や業務の免除、有給の消化日数など、さまざまな点で見解の相違からトラブルになるリスクもあります。早期退職制度を使って退職する社員に対しては面談を行って十分に説明をし、制度に対して理解を深めてもらうことが大切です。
会社の承認を必須条件とする
早期退職制度を設けることで、会社の中核を担う幹部社員、経験や知識が豊富で現場の主力となっている社員が辞めてしまうおそれもあります。会社の承諾を得ることで早期退職できるといった条件を設けることで、中核を担い主力となる社員の退職を防ぐことができます。
業務の引継ぎ体制を整備する
早期退職制度の利用者から、業務の引継ぎをスムーズに行えるようにすることも重要です。
例えば、業務マニュアルの整備や引継ぎ期間を考慮した退職日の設定などにより、社員の負担を軽減できます。早期退職者が出た後でも円滑に業務を続けられるように、引継ぎ体制を整備しましょう。
早期退職制度についてよくある質問
ここでは、早期退職制度についてよくある質問と回答をご紹介します。
Q1.早期退職は自己都合・会社都合のどちらに該当しますか?
早期退職制度では退職を自主的に希望する社員が対象となるため、原則として自己都合での退職として扱われます。
Q2.早期退職制度の対象年齢を教えてください
早期退職制度の対象年齢は企業が自由に設定できます。40代から50代などの条件を設定することが一般的です。
Q3.早期退職制度を実施する際の注意点は何ですか?
早期退職する社員の守秘義務や競合避止義務について明確に定めておくことや、十分な説明の実施などが注意点として挙げられます。また、会社の承認を必須条件にすることや、引継ぎ体制の整備なども重要です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
雇用調整施策の一つとして早期退職制度を検討しましょう
早期退職制度は、企業にとって長期的な人件費の抑制や組織の活性化といったメリットがある制度です。ただし、早期退職制度の目的や内容があいまいであったり、説明が不十分であったりした場合、思ったような効果が得られない場合もあります。また、社員の不信感を招きトラブルに発展してしまうといったリスクもあるため、適切な制度設計や十分な説明が重要です。
社会情勢や人々の価値観の変容から、企業のあり方も変わってきています。雇用調整施策や福利厚生施策の一環として、早期退職制度という選択肢も考慮に入れておきましょう。
メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!
監修者
HRナレッジライン編集部
HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。
編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。
法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。
- 記事をシェアする