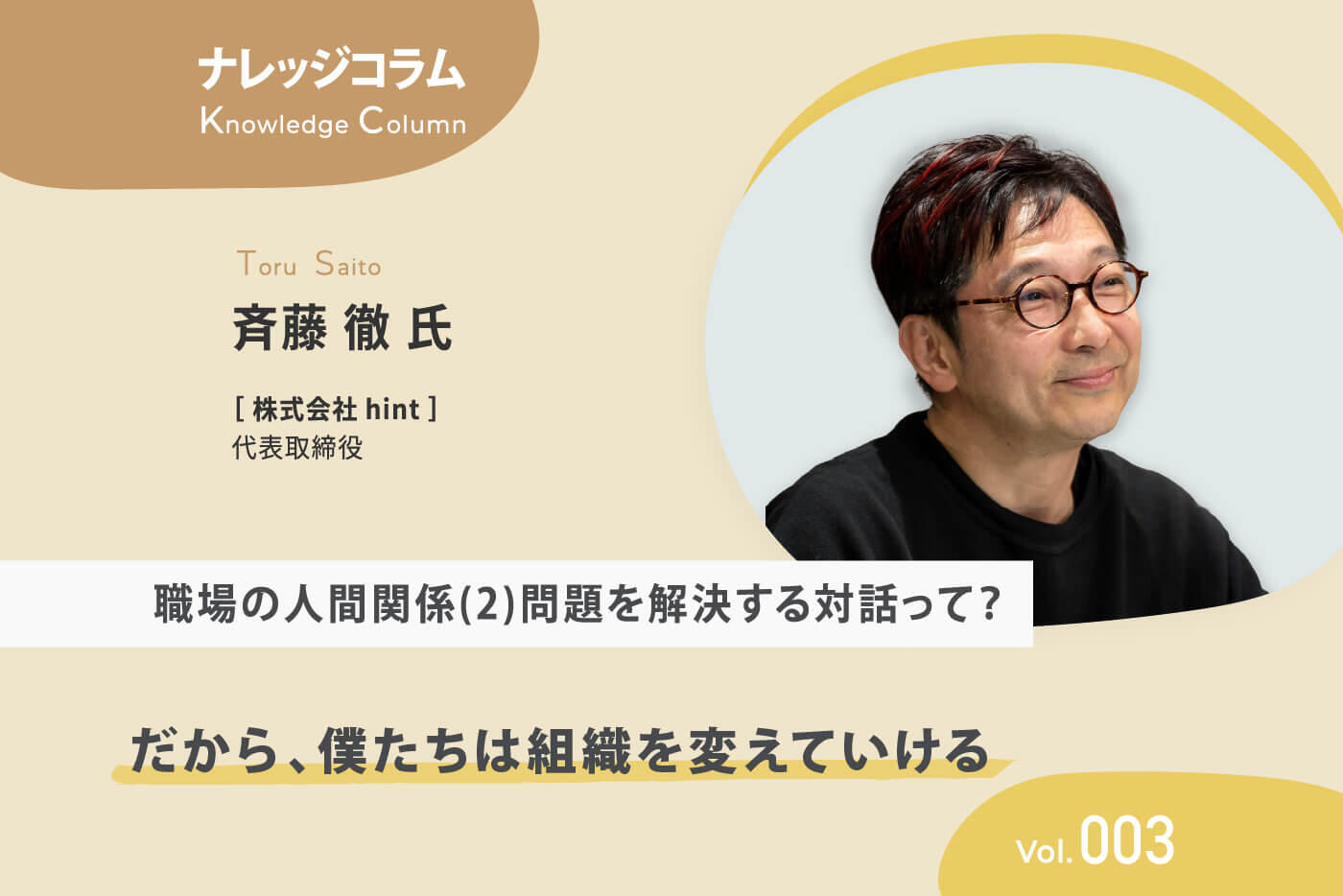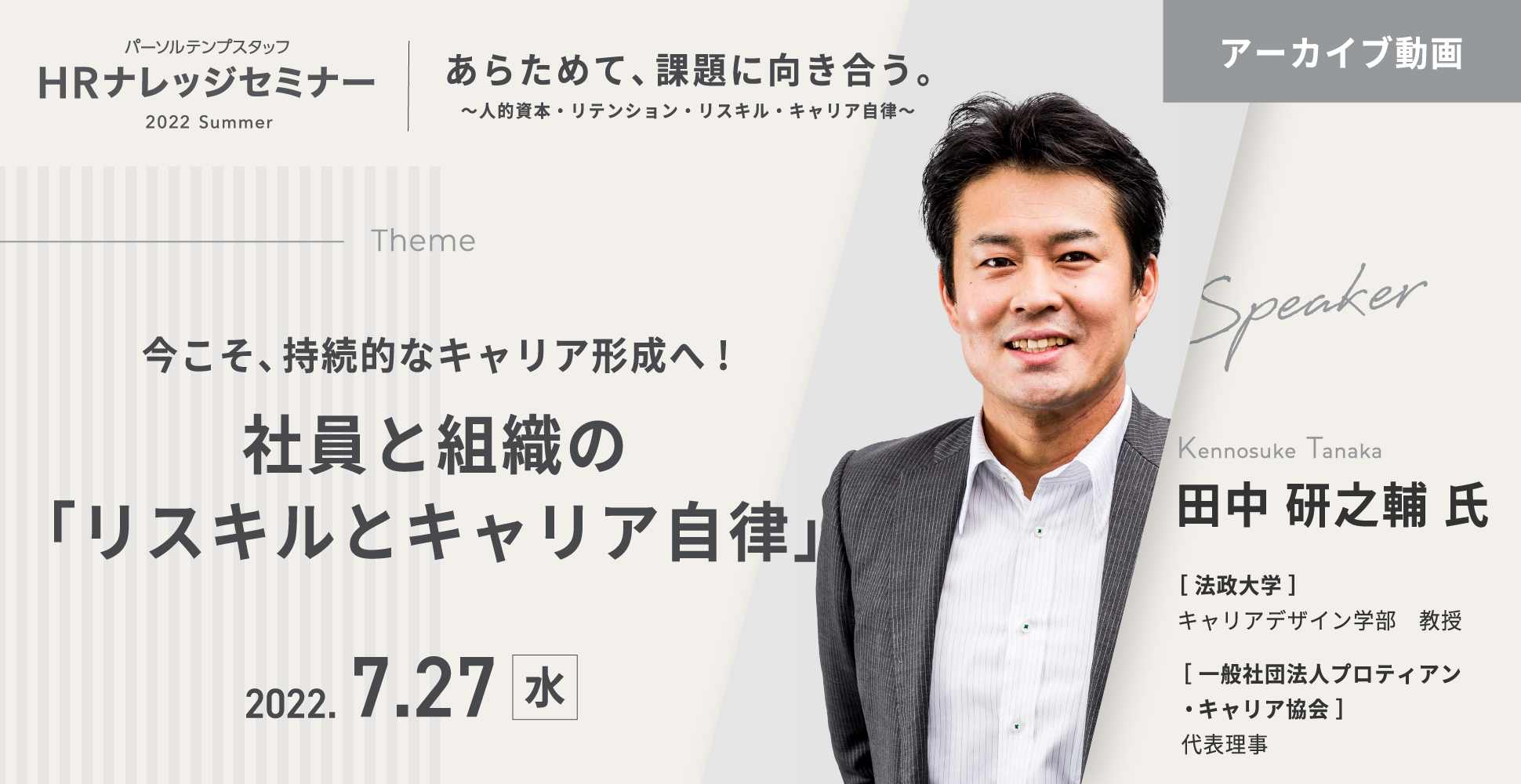HRナレッジライン
カテゴリ一覧
【ナレッジコラム】
マネジメントの未来価値探求vol.002
指示・命令は時代遅れ? ~組織を活かす「対話の力」の本質~
公開日:2025.11.12
- 記事をシェアする

ナラティブ・エル・セッションズ合同会社 代表
著者/組織開発・人材開発コンサルタント
成瀬 岳人 氏
HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。著者/組織開発・人材開発コンサルタントで、マネジメントの探究コミュニティ「Narrative“L”Sessions」を主催する成瀬岳人氏による「マネジメントの未来価値」について6回連載でお届けします。
昨今、マネジメントは“罰ゲーム”と揶揄されていますが、本コラムでは マネジメントのやりがいや学び、成長など、重要性やポジティブな側面に陽の光を当てていきます。
第2回は「指示・命令は時代遅れ? ~組織を活かす「対話の力」の本質~」です。
▼バックナンバーはこちら
vol.001:マネジメント・キャリアに陽を当てる ~人と組織を幸せにできる管理職の可能性~
指示・命令は時代遅れ? ~組織を活かす「対話の力」の本質~
「対話重視」という言葉に戸惑うマネジャーたち
前回、私は「良いマネジメント体験は伝播する」という話をしました。AIが働き方を変える時代においてマネジメントの価値がむしろ高まる理由として、人間にしかできない「共感」「創造性」「判断力」を組織で最大化する役割の重要性をお伝えしました。
今回は、その良いマネジメント体験を生み出す核となる「対話」について探求していきます。
「心理的安全性を高めなさい」「もっと対話を重視しなさい」「メンバーに寄り添いなさい」——人事部門や経営層からそう言われ、戸惑いを感じているマネジャーは少なくありません。
先日、ある製造業のマネジャーからこんな相談を受けました。
「成瀬さん、正直に言うと、対話を重視しろと言われても、何をどうすればいいのか分からないんです。1on1も始めましたが、メンバーの話をひたすら聴いているだけで、これでいいのかと不安で。それに、厳しいことを言うとハラスメントになるんじゃないかと怖くて、言うべきことも言えなくなってしまって・・・」
この悩みは、決して特殊なものではありません。多くのマネジャーが「対話重視」という言葉の本質をつかみきれないまま、手探りでマネジメントをしているのが現状です。

※筆者&AI作成
「対話重視」をめぐる3つの誤解
まず、現場でよく見られる「対話重視」の誤解を3つご紹介します。皆さんの周囲でも心当たりがあるかもしれませんので、普段のコミュニケーションを思い返してみてください。
誤解1:対話とは「メンバーの話をひたすら聴くこと」
ある日、私が支援している企業のマネジャーAさんは、部下との1on1を30分間、ほとんど無言で相手の話を聴き続けていました。終了後、「今日も話を聴くことができました」と満足そうでしたが、メンバーの表情は曇っていました。
後日、そのメンバーに話を聴くと、こう言いました。「Aさんは優しいんですけど、正直、私が何を期待されているのか分からなくて。ただ話を聴いてもらうだけじゃなくて、方向性を示してほしいんです」
対話は「聴くこと」だけではありません。聴くことと問うこと、そして時には明確に伝えることの、相互作用なのです。
誤解2:心理的安全性とは「厳しいことを言わない優しい環境」
「心理的安全性を高めるために、メンバーを傷つけるようなことは一切言わないようにしています」——こう語るマネジャーBさんのチームでは、誰も意見を言わなくなっていました。
心理的安全性の研究者エイミー・エドモンドソン氏は、心理的安全性を「失敗を恐れずに挑戦できる環境」と定義しています。決して「何を言っても許される甘い環境」ではありません。
むしろ、本当に心理的安全性が高い組織では、建設的な対立や率直なフィードバックが活発に行われています。「失敗しても次に活かせる」という安心感があるからこそ、厳しい現実とも向き合えるのです。
誤解3:対話をすれば自然に成果が上がる
「対話の時間は増やしたのですが、なかなか成果に結びつかなくて・・・」という声もよく聴きます。
対話は確かに重要ですが、目的のない対話は時間の浪費になります。対話を通じて「何を目指すのか」「どんな変化を生み出したいのか」が明確でなければ、それは単なる雑談になってしまうのです。
私が出会った「対話の力」を体現したマネジャー
ここで、私のサラリーマン時代に出会った、対話の本質を体現していたマネジャーの話をさせてください。
鈴木さん(仮名)との対話が教えてくれたこと
私が新規事業の立ち上げで行き詰まっていた時のことです。3ヶ月間、ほとんど成果が出せず、週次ミーティングで上司の鈴木さんに報告するのが苦痛でした。
その日も、言い訳がましい報告をする私に、鈴木さんは静かに聴き入っていました。報告が終わった後、鈴木さんは言いました。
「成瀬君、今の報告を聴いて、正直に言うと残念な気持ちになった。君は『なぜうまくいかないか』は一生懸命説明してくれたけど、『これからどうするか』が見えなかった」
厳しい言葉でした。でも、鈴木さんは続けました。
「でもね、この3ヶ月の試行錯誤は決して無駄じゃない。この失敗から何を学んだ?そこから見えてきた、次の一手は何だと思う?」
この問いかけで、私の視点は一気に変わりました。過去の言い訳ではなく、未来の可能性に目が向いたのです。
そして、私がさまざまな顧客との商談経験から気付いたアイデアを話し始めると、鈴木さんは「それ、面白いね」と言いながら、具体化するための質問を次々と投げかけてくれました。30分後、私は明確な次のアクションプランを持ってミーティングルームを出ました。
鈴木さんは、厳しさと支援を両立させていました。私の感情に寄り添いながらも、成果への責任を曖昧にせず、そして私自身の思考を引き出すことで、自律的な行動を促してくれたのです。 これこそが、真の「対話の力」だと、今でも確信しています。
対話の本質:3つの要素の統合
鈴木さんの対話から学んだこと、そして多くのマネジャーを支援してきた経験から、私は「効果的な対話」には3つの要素が必要だと考えています。

※筆者&AI作成
- 探索する(Explore)
メンバーの考え、感情、状況を理解する。表面的な言葉だけでなく、その背景にある本音や葛藤にも目を向ける。
「今、何が一番の課題だと感じている?」
「その選択をした理由は?」
「理想的には、どうなっていたい?」 - 挑戦する(Challenge)
現状維持ではなく、成長と成果に向けて、建設的に問いかけたり、期待を明確に伝える。
「その方法で、本当に目標は達成できると思う?」
「次回は、こういう視点も加えてほしい」
「君ならもっとできるはずだと、私は信じているよ」 - 支援する(Support)
一人で抱え込ませず、具体的なサポートを提示する。心理的にも実務的にも、「一緒に乗り越える」姿勢を示す。
「困ったら、いつでも相談してほしい」
「この部分は、私が○○さんと調整するよ」
「まずは試してみて、1週間後に状況を確認しよう」
この3つがバランスよく組み合わさった時、対話は単なる会話ではなく、メンバーの成長とチームの成果を同時に生み出す強力なツールになります。
「心理的安全性」と「説明責任」の両立
心理的安全性について、もう一度整理しましょう。
エドモンドソン氏は、最も学習効果が高いのは「心理的安全性が高く、同時に説明責任も高い状態」だと指摘しています。つまり、「失敗しても大丈夫」という安心感と、「成果に対する責任は持つ」という緊張感が共存している状態です。
私が推奨している「建設的フィードバックの4ステップ」をご紹介します。
- ステップ1:事実を共有する 「先週の報告書、締め切りに2日遅れたね」
- ステップ2:影響を説明する 「そのため、顧客への提案が間に合わなくなった」
- ステップ3:期待を明確にする 「次回は、難しそうなら早めに相談してほしい」
- ステップ4:支援を提示する 「スケジュール管理で、何かサポートできることはある?」
このアプローチなら、厳しい現実を伝えながらも、相手を追い詰めず、次への学びにつながります。
対話は「戦略的投資」である
「そんな対話の時間、取れないんです」——そのような声も聴こえてきそうです。
確かに、日々の業務に追われる中で、対話の時間を確保するのは簡単ではありません。しかし、考えてみてください。
週に1時間の対話が、今後10時間の手戻りを防ぐかもしれません。月に4時間の1on1が、メンバーの離職を防ぐかもしれません。対話は「コスト」ではなく「投資」なのです。
私自身、マネジャー時代に最も後悔しているのは、「忙しい」を理由にメンバーとの対話を後回しにしてしまったことです。その結果、小さな問題を見逃し、大きな問題に発展させてしまったことがありました。「あの日の1on1を自分の都合でリスケしなければ・・・」、「あの日のコミュニケーションで、曖昧にせず、もっと踏み込んで話していれば・・・」、そんな後悔がいくつもあります。ぜひ、この記事をお読みいただいた皆さんには、「今、対話すべき時」を逃さないでいただきたいです。
対話は、人と組織を幸せにする技術
「指示・命令は時代遅れか?」——この問いに対する私の答えは、「指示・命令が不要になったわけではなく、それだけでは不足になった」です。
指示・命令には依然として必要な場面があります。しかし、メンバーの自律性を高め、創造性を引き出し、持続的な成長を促すには、対話が不可欠なのです。
そして、「厳しいことを言ってはいけない」も大きな誤解です。相手を信じて、相手のことを思って伝えなければいけないことは、その意図を明確にした上で、ハッキリと伝える必要があります。
テクノロジーが定型業務を代替する時代において、人にしかできない「共感」「創造性」「判断力」の価値を高める——それがこれからのマネジメントの役割です。
そして、その役割を果たす最も強力な手段が、「対話」なのです。
対話は、単なるコミュニケーション技術ではありません。人と組織を幸せにする、これ以上ない価値ある営みなのです。
あなたの「次の一歩」は?
この記事を読み終えた皆さんにお願いしたいことがあります。
今週、一人でいいので、メンバーと「目的ある対話」をしてみてください。30分でも15分でも構いません。
対話を始める前に、自分に問いかけてください。「今日、この対話で何を実現したいのか?」
そして、3つの要素——探索し、挑戦し、支援する——を意識してみてください。
完璧である必要はありません。まずは一歩、意識して踏み出してみることが大切です。
その一歩が、あなたとメンバーの関係を変え、チームを変え、そして組織全体に良い影響を伝播させる起点になるのですから。
次回は、「1on1の真価:相互成長を生み出す個別支援」をテーマに、より具体的な1on1の実践方法について探求していきます。
Profile

ナラティブ・エル・セッションズ合同会社 代表
著者/組織開発・人材開発コンサルタント
成瀬 岳人 氏
22年間のサラリーマン経験を経て2025年4月に独立し、マネジメントの探求コミュニティ「Narrative "L" Sessions」を主宰。事業構想修士(MPD)と実務教育学修士(MPE)の二つの修士号を持つ。現在は一般社団法人プロティアン・キャリア協会CDOや「全員マネジメント」を標榜する株式会社NOKIOOのパートナー講師も務める。主な研究テーマは「ウェルビーイング」「マネジメント」「AI」。
- 記事をシェアする