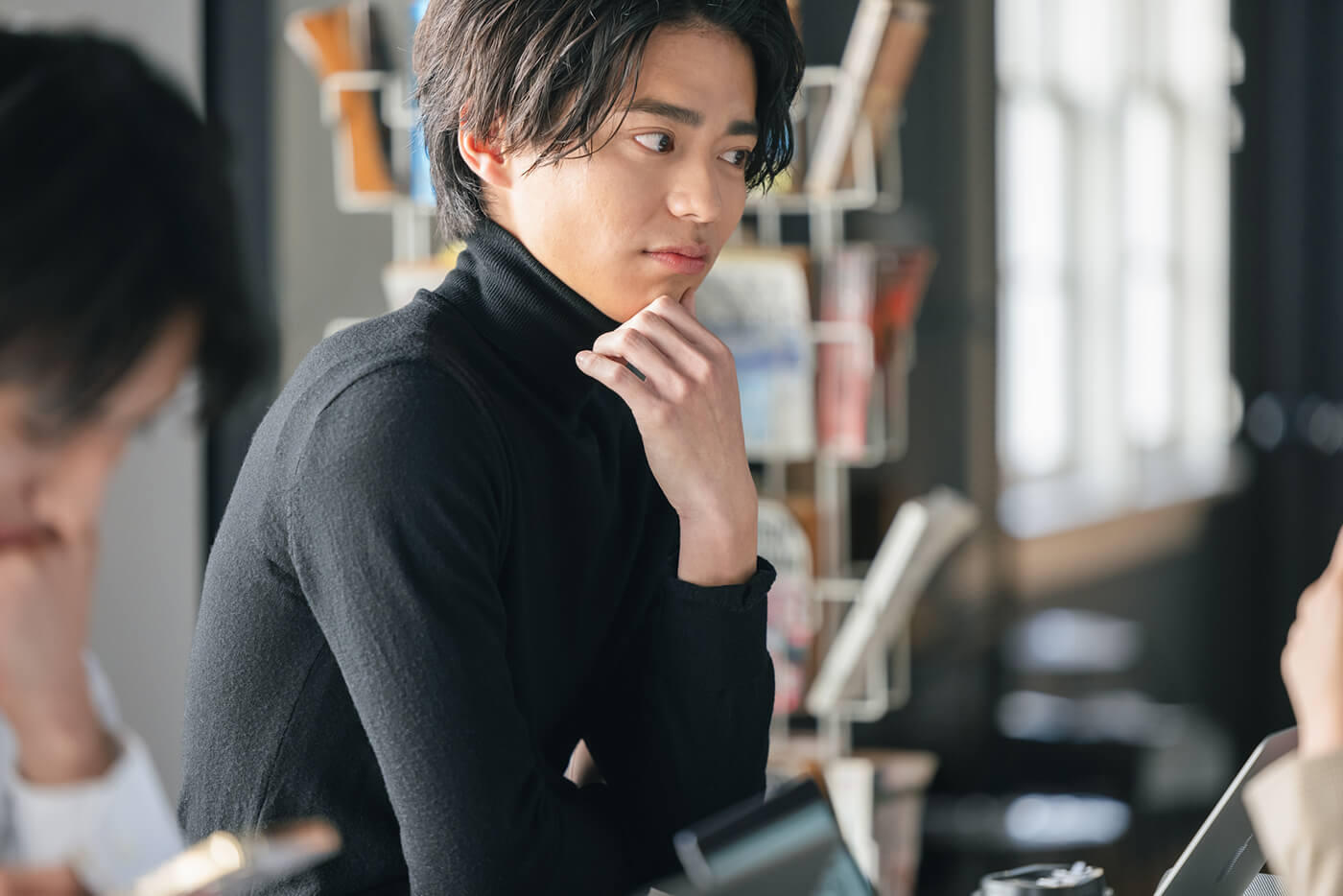HRナレッジライン
カテゴリ一覧
金融教育を企業で実施するメリットとは?社員へ教えるべき知識やセミナー実施方法
公開日:2025.02.27
- 記事をシェアする

いま、企業の福利厚生の一環として、金融教育が求められています。社員に金融・経済の知識を身に付けて将来の生活設計に役立ててもらい、安心して長くはたらき続けてもらうためにも、金融教育は大切な取り組みです。
本記事では、企業における金融教育についての基礎知識と、実践する方法について具体的に紹介します。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
目次
金融教育とは
企業における金融教育とは、社員に金融リテラシーを身に付けてもらうための教育を指します。
金融リテラシーとは、お金・経済の知識を身に付け、必要な商品・サービスを適切に選択できる力のことです。
いま、資産計画や将来設計を行い今後のリスクに対策することは、より豊かな生活やよりよい社会づくりにとって重要とされています。例えば、2022年からは高等学校の授業に金融教育が盛り込まれるなど、国を挙げて金融リテラシーを高めるための取り組みがされています。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
日本の金融リテラシーの現状と金融教育が求められる背景
日本の金融リテラシーの現状はどうなっているのでしょうか。
金融広報中央委員会が発表した「金融リテラシー調査2022年」の結果によると、7〜9割の人は日頃から家計管理に取り組んでいることが分かります。しかしその一方で、「金融・経済の基礎、保険、ローン・クレジット、資産形成」に関する適切な理解ができている人は5割前後でした。
ローンや保険商品購入・資産運用を行う際に、他の金融機関や商品と比較検討ができている人は5~7割程度、自分の年金について詳細に認識できている人は4割程度に留まります。
加えて、株式・投資信託・外貨預金などの投資商品を購入したことがある人は2~3割程度に過ぎず、そのうち2~3割程度は商品特性を理解しないまま購入していることも分かりました。
これらのデータから、日本の投資や資産形成にまつわる金融リテラシーには大きな課題があるといえます。
※参考:金融広報中央委員会 知るぽると|「金融リテラシー調査2022年」の結果
金融教育が求められている
先ほど紹介したデータの通り、多くの人が投資や資産形成について理解度がそれほど高くはない現状があります。さらに、内閣府が令和4年10月に実施した「国民生活に関する世論調査」によると老後や今後の資産形成について不安を抱えている人は多くいる状況です。
このような現場に対し政府は、資産運用に関して「NISAの拡充」「顧客の立場に立ったアドバイザーの普及・促進」「金融経済教育の充実」といった取り組みを推進しています。
今後も、社員が適切に金融商品を選択して資産形成ができるよう、金融リテラシーを高めるための教育が必要だといえるでしょう。
※参考:内閣府|国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査)
企業の福利厚生の一環で金融教育を実施するメリット
ここからは、企業の福利厚生の一環で金融教育を実施するメリットについて解説します。
社員エンゲージメントの向上
金融教育の実施によって、社員エンゲージメントの向上が期待できます。社員エンゲージメントとは「会社に貢献しよう」という社員一人ひとりの意欲のことです。
例えば、会社に金融教育のサポートがあれば、社員はお金に関する不安を職場で相談できたり、知識を教えてもらえたりします。その結果、社員の会社に対する信頼度が高まり、安心感を持って長期的にはたらけるようになると考えられます。
社員の人生の充実につながるだけではなく、採用した社員が長期的に会社に定着して貢献してくれることは、企業にとってもメリットになるでしょう。
採用活動における自社の訴求力の強化
金融教育の実施体制があることは、採用活動の中でも強みになると考えられます。
大学生を対象に行われた調査によると、これから就職先を選ぶ学生は企業に対して重視することとして「安心・安定」を挙げる人が最も多く、2013年と比べほとんど倍の割合に増えています。
企業で長期的に金融教育に取り組んでいれば「資産形成のサポートが手厚く、安心してはたらける企業だ」と求職者に思ってもらえ、優秀な人材を採用する上での武器になるでしょう。
企業が行う金融教育で具体的に教えるべきポイント
それでは、企業の金融教育で教えるべきポイントとして、どのような項目が考えられるのでしょうか。具体例を紹介します。
20代の若手社会人向け
20代の若手社会人向けには、次のような項目が考えられます。
- 給与明細の見方
- 家計管理
- 資産形成の基本(長期・積立・分散)やNISA・iDeCoなど
- 社会保険と民間保険
- クレジット
- 奨学金
- 金融トラブルの防止など
給与明細の見方や、家計管理の基本など、主に将来の資産形成に取り組み始める上での基礎知識を教えることが推奨されます。
30〜40代の中堅社会人向け
30〜40代の中堅社会人向けには、次のような項目が想定されます。
- 家計の現状把握
- 外部知見(お金の専門家)の活用を通じた将来設計・資産形成の考え方
- 社会保険と民間保険
- 各種ローン
- 金融トラブルの防止など
この世代は結婚・子育て・子どもの教育など、大きな出費が生じやすいと考えられます。そのため、ファイナンシャルプランナーなど外部の専門家のサポートのもと、定期的に家計の現状把握を行って家計の見直しを図るといったような、実践的な金融教育を提供するとよいでしょう。
50代以上のベテラン社会人向け
50代以上のベテラン社会人向けには、次のような項目が考えられます。
- 定年退職後の生活を見据えた年金などの社会保険
- 退職金
- 税金の仕組み
- 資産寿命の延伸
- 相続・贈与・終活など
この世代は、定年退職を意識しだし、老後資金の準備への関心が高まります。そこで、定年退職後の生活を見据え、年金や退職金、資産寿命の延伸などについて知ってもらえる内容を提供するとよいでしょう。
企業で金融教育を実施するならFinanstaがおすすめ
企業で金融教育を実施するには、専門知識に基づいた正しい教育が欠かせません。効果的な方法として、金融教育の専門家がいる企業へセミナーや社員のサポートを委託することがおすすめです。
パーソルテンプスタッフでは、企業向け金融教育サービス「Finansta」をご提供しています。
▼金融教育サービスFinansta

従業員のお金の教養を高めマネー&ライフプランニングを支援
Finanstaは、金融リテラシー教育を通じて、社員やその家族のライフプラン設計をサポートするサービスです。社員一人ひとりの経済的な不安を解消することにより、社員エンゲージメントの向上に貢献します。
Finanstaの具体的な3つの提供内容をご紹介します。
マネーセミナーの提供
企業に訪問してマネーセミナーを実施可能です。
HR領域を専門としてきた経験を活かし、細かな部分まで踏み込んだマネーセミナーをご提供します。
【セミナー内容の例】
- 確定拠出年金の金融商品の選び方
- 個人確定拠出年金(iDeco)の活用方法
- 保険の選び方
- 住宅の選び方
金融教育動画コンテンツの制作
社員が好きな時間に動画を視聴して金融教育を受けられるよう、動画コンテンツを制作いたします。社員の年代や世帯構成別にパーソナライズしたコンテンツを制作するため、確実に届く金融教育が可能です。
社員が面しているライフイベントにちなんだお金に関する公的制度や、企業の福利厚生などについての情報を提供することで、社員一人ひとりが「必要な自助努力は何か?」と考え、行動変容につながると期待できます。
専門家によるアドバイスやアウトソーシング
パーソルテンプスタッフのファイナンシャルプランナーが、お金に関する各種相談を行います。個別相談会や、ファイナンシャルプランナーを交え社員同士で意見を交わす座談会を実施しています。
さらに、企業の福利厚生を理解したファイナンシャルプランナーが、社員からの個別相談、メール相談、電話相談などに対応するアウトソーシングサービスも提供が可能です。
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
人事担当者必見!
お役立ち資料を無料ダウンロード
社員に届く金融教育が重要
本記事では、企業が金融教育に取り組む重要性について解説しました。
社員が安心感・満足感の持てる金融教育を提供するためには、社員の年代や家族構成、ニーズなどを理解し状況や関心に合わせたコンテンツを用意することが必要です。
企業で金融教育を実施するなら、パーソルテンプスタッフの金融教育サービス「Finansta」がおすすめです。
金融機関ではないからこそ中立な立場で情報提供ができるため、偏りのない情報をもとに金融リテラシー向上をご支援できます。
企業の金融教育実施についてお悩みの担当者さまは、ぜひパーソルテンプスタッフの金融教育サービス「Finansta」の導入をご検討ください。
▼金融教育サービスFinansta

従業員のお金の教養を高めマネー&ライフプランニングを支援
人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください
- 記事をシェアする